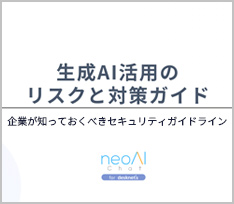業務改善とは?
成功に導く5つのステップと実践方法
業務の効率を高め、生産性を向上させるためには、現在のフローやプロセスを見直すことが重要です。特にムダやムリ、ムラを徹底的に排除することで、組織全体のパフォーマンスを大きく底上げできます。
しかし、日々の業務に追われていると、全体を客観的に把握できず、改善の手が打てないまま問題を放置してしまいがちです。そこでまずは、具体的なステップや実践方法を知り、どこから取り掛かればよいのか方向性を明確にしていくことが大切になります。
本記事では、業務改善の基本的な意味から、その必要性と背景、さらに具体的な5つのステップや実践方法までを幅広く解説します。業務改善がもたらす成果を理解し、継続的に取り組むためのポイントをしっかり押さえてみましょう。
業務改善とは

まずは、業務改善の定義や目的について押さえることから始めましょう。
業務改善とは、組織やチームの活動の中で生じる非効率や無駄を洗い出し、継続的に修正を加えていくプロセスを指します。具体的には、生産性を高めるためのフロー再設計や情報共有の仕組み化など、さまざまな角度からアプローチできます。
大切なのは、業務をただ短縮したり削減したりするだけではなく、組織のゴールや戦略に合った形で最適化することです。例えば、業務内容を棚卸しして必要な工程と不必要な工程を明確に区別すると、効果的な改善施策が見えてきます。
こうした工夫を通じて、企業が現場レベルの課題を解決すると同時に、差別化要因や新たなビジネスチャンスの創出へと繋げることも可能になります。結果的に、持続的な成長と従業員のモチベーション向上が期待できるのです。
業務改善の意味と目的
業務改善の本質は、現行のプロセスを分析して問題点を特定し、改善に向けたアクションを積み重ねることです。目的としてはムダ・ムリ・ムラといった非効率を取り除き、コスト削減や品質向上をもたらす点が挙げられます。
特に、生産年齢人口が減少する中で持続的に企業競争力を維持するためには、限られたリソースを最大限に生かすことが必要です。業務改善を進めることで、組織全体の生産性アップだけでなく、従業員一人ひとりの付加価値創出にもつながります。
さらに、改善活動を通して得られたノウハウは、社員のスキルアップだけでなく、企業文化としての “常に革新を続ける姿勢” を育む役割も担います。これらの要素が相乗効果を生み、最終的には企業や組織が社会的に評価される結果へと繋がるのです。
製造業の業務改善についてのおすすめ資料
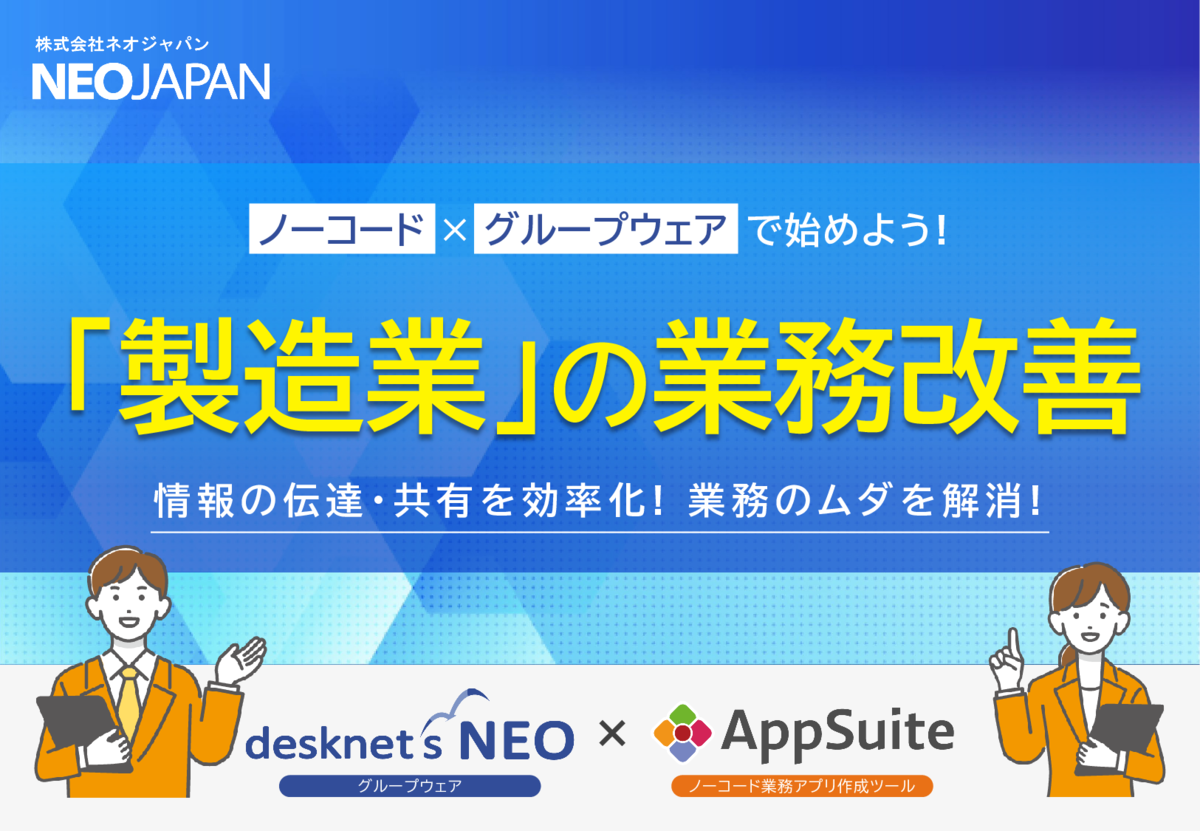
ノーコード×グループウェアで始めよう!
「製造業」の業務改善
紙やExcelでの書類管理、電話やメールでの連絡…。製造業の現場から聞こえてくる、社内での情報共有やペーパーレスに関する課題は、ノーコードとグループウェアで解決できます!
業務改善が求められる背景

社会環境や働き方の変化など、業務改善の必要性が高まっている理由を振り返ります。
近年、少子高齢化に伴う労働力不足や競争激化、働き方改革の推進など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。これまでの慣習的な作業や属人的なノウハウだけでは、多様化する課題を解決しきれない状況が生まれています。
さらに、テクノロジーの進化により、新たなビジネスモデルやサービスが登場しています。これらに迅速に対応するためには、旧来のプロセスを見直し、変化に順応できる柔軟な組織体制が欠かせません。
このような背景の中で、業務改善の取り組みは、単なるコスト削減や作業効率化だけでなく、企業としての継続的成長を担保するための戦略的要素としての意味合いも強くなっているのです。
業務改善を進める5つのステップ
業務改善を具体的に実行するために役立つ代表的な進め方を順番に解説します。
業務改善を実際に進めるには、全体像を見わたしてから個別の課題へ取り組むことがポイントです。各ステップを着実に踏むことで、改善活動の抜けや漏れを防ぎ、効果を最大化することができます。
最初は現状把握と課題の整理が中心ですが、改善案の検討や実行後の振り返りまでを一連の流れとして捉えることで、組織全体で改善サイクルを回せるようになります。
ここからは、5つのステップそれぞれのポイントについて、具体的な方法や着眼点を順番に解説していきます。
1.現状把握
最初に行うべきは、全業務の可視化です。担当者や部門ごとの業務内容、処理フロー、使用ツールなどをリストアップし、どのようなフローで成果物や情報が流れているかを明確にします。
経営者や管理職だけでなく、実務者の生の声をヒアリングすることも重要です。現場レベルでの苦労やボトルネックを知ることで、後々の改善策に具体性をもたせることができます。
現状分析には、フローチャートや業務日誌、ツール使用状況のデータなどを積極的に活用しましょう。定量データと定性情報を組み合わせると、問題点をより正確に把握できます。
業務改善についてもっと知りたい方はこちら:業務の見える化とは?その効果とうまく進めるコツを解説
2.課題の整理
現状把握で得た情報をもとに、課題を分類し可視化するステップです。例えば、作業ミスの多発、コミュニケーション不足、システムの使いづらさなど、いくつかのカテゴリに分けて整理します。
全課題を一度に解決するのは難しいため、優先順位をつけるのも大切です。影響度や緊急度、改善コストなど、複数の視点から課題を評価し、改善の方向性をまとめましょう。
この工程では、ロジックツリーやKPT(Keep, Problem, Try)などのフレームワークが役立ちます。情報を分かりやすく整理しやすくなるため、チーム間の認識共有がスムーズに進むでしょう。
3.改善案の検討
整理した課題に対して、どのように対処すればよいのか、具体的なアイデアを出し合う段階です。ECRS(排除・結合・交換・簡素化)などの手法を参考に、複数の切り口から解決策を導き出します。
改善策を検討するときは、コストや必要とされるリソース、期待できる効果などを見極めることが求められます。短期的な成果だけでなく、中長期的にメリットがあるかどうかを評価することも重要です。
複数案を比較し、最適なものを選ぶには、組織の戦略や価値観との整合性も考慮すると失敗リスクを下げられます。導入後のシステム運用や教育体制の確立も、同時に検討しておくとよいでしょう。
4.実行計画の策定
改善案が固まったら実行計画へ落とし込む作業が必要になります。具体的な担当者や期限、必要な予算・リソースなどを細かく設定し、進行管理の基盤を作りましょう。
ガントチャートやタスク管理ツールなどを使うと、どのタスクがどの時点でどのように行われるかが可視化され、メンバー間の連携が円滑になります。
実行計画があいまいだと、責任の所在が不明確になったり、スケジュールが大幅に遅延したりするリスクが高まります。必ずチーム全体と合意を取り、実現可能なスケジュールを組むことが基本です。
5.実行と振り返り
計画をもとに改善策を実行に移し、結果を定量的・定性的に追跡します。手順を明確化し、必要に応じて従業員へのトレーニングやシステムの微調整を行いましょう。
実行後には、必ず振り返りの時間を設けます。期待どおりの成果が得られたのか、想定外の問題が発生していないかなどを検証すると同時に、さらに改良の余地があるかを探っていきます。
こうした振り返りを通じて、業務改善のサイクルを継続的に回せるようになり、個別の施策が組織の成長や人材育成にも寄与するようになります。
業務改善についてもっと詳しく

desknet's NEO ユーザー事例集
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOを活用し業務改善に成功したお客様の導入事例を集めました。
業務改善の具体的な実践方法

実際に業務を改善する際に役立つ具体的なアプローチやITツールを紹介します。
理想的な業務改善を目指すには、現状を可視化した上で優先度を決め、運用しやすい形で落とし込むことが鍵を握ります。個別の手法を組み合わせることで、さまざまな課題に柔軟に対応可能です。
ここでは、業務フローの“見える化”から、マニュアル作成、AI活用、そしてアウトソーシングなど、実際の現場でも活用されている代表的な方法を紹介します。
これらを実践に移す際は、自社や自部署の特性を踏まえて微調整することが大切です。また、取り組みの効果を早く得るためにも、小さな単位でテストを繰り返しながら徐々に拡大する方法もよく用いられます。
業務の見える化
業務フローや各種データを可視化することで、問題箇所が自然と浮かび上がってきます。フローチャートやダッシュボードなどを用いて、どの工程に無駄が多いかをリアルタイムで把握できる環境を作ることが大切です。
データドリブンなアプローチを実践できるようになれば、具体的な数値に基づいた根拠ある改善提案を行えます。定例会議で定期的に状況を共有し、問題が発生するたびに即座に対策を講じる文化づくりを促進します。
見える化は単純に“情報を見せる”だけではなく、“何をどのように表示するか”というポイントが重要になります。利用者目線に立ったデータ整理や、必要に応じたアクセス権限の設定など細かな配慮も忘れないようにしましょう。
業務の優先順位付け
数多くの業務の中で、どこから取り組めば最も効果が大きいのか迷うことは多いでしょう。優先順位を決める際には、業務の重要度と緊急度、そしてコストや効果の大きさをしっかり評価します。
案件を優先度ごとに整理するには、タスク管理ツールやExcelなどで簡単なマトリックス表を作成する方法が一般的です。これにより、“すぐ対応すべき業務” と “後回しでも問題ない業務” の区別がつきやすくなります。
優先度を決める際には、主観的な判断に陥らないよう客観的なデータや部門間の意見交換も大切です。公平な基準を設定しておくと、メンバー間での齟齬を最小限に抑えられます。
業務のマニュアル化
マニュアル化は属人化を防ぎ、業務品質を安定させるうえで欠かせない取り組みです。ベテラン社員のノウハウや手順を明文化し標準化しておくことで、新人や異動者でも一定レベル以上のパフォーマンスを発揮できます。
文字だけでなく、図や画像、動画などを使いながら分かりやすい資料を整備すると、教育コストの低減にもつながってきます。更新履歴を管理し、常に最新の情報を提供できるようにすることも重要です。
マニュアル化が進むと、煩雑な問い合わせ対応に追われる時間が大幅に減り、生産性が高まります。その分リソースを高度な業務や新規プロジェクトに振り向けられるため、企業全体の成長に寄与するでしょう。
生成AIの活用
近年注目されている生成AI(人工知能)は、文章作成やデータ処理を半自動化する強力なツールです。メールの下書きやチャットボット対応、データのレポート作成など、単純作業にかかる時間を大幅に削減できます。
ただし、生成AIの導入にあたっては、セキュリティ面や運用コスト、導入後の教育など留意すべき点が多くあります。何をAIに任せるか、どこまで人間が介在するかを明確に区分しておくと効率が上がります。
AIが得意とする部分を積極的に活用し、社員がよりクリエイティブで戦略的な業務に注力できるようにすることこそが、真の業務改善につながるポイントです。
生成AIで実現する業務効率化~導入を成功に導く方法~
企業におけるAI活用ガイド【2025年版】:国内外事例と成功へのポイント
アウトソーシング
社外の専門家やサービスを活用して、自社では手が回らない業務や専門的な知識が必要な業務を委託する選択肢もあります。アウトソーシングのメリットは、必要なときに必要なスキルを外部から調達できることです。
ただし、業務の中核部分まで外注すると、自社内にノウハウが残らないリスクがあります。外注すべき点と社内で取り組むべき点を明確に切り分けることが大切です。
費用対効果を見極めつつ、業務負荷を軽減し、人材をコア業務に集中させるための有力な手段として活用できれば、組織全体のプロセスがよりスムーズに回るでしょう。
生成AIの基礎知識についてもっと詳しく
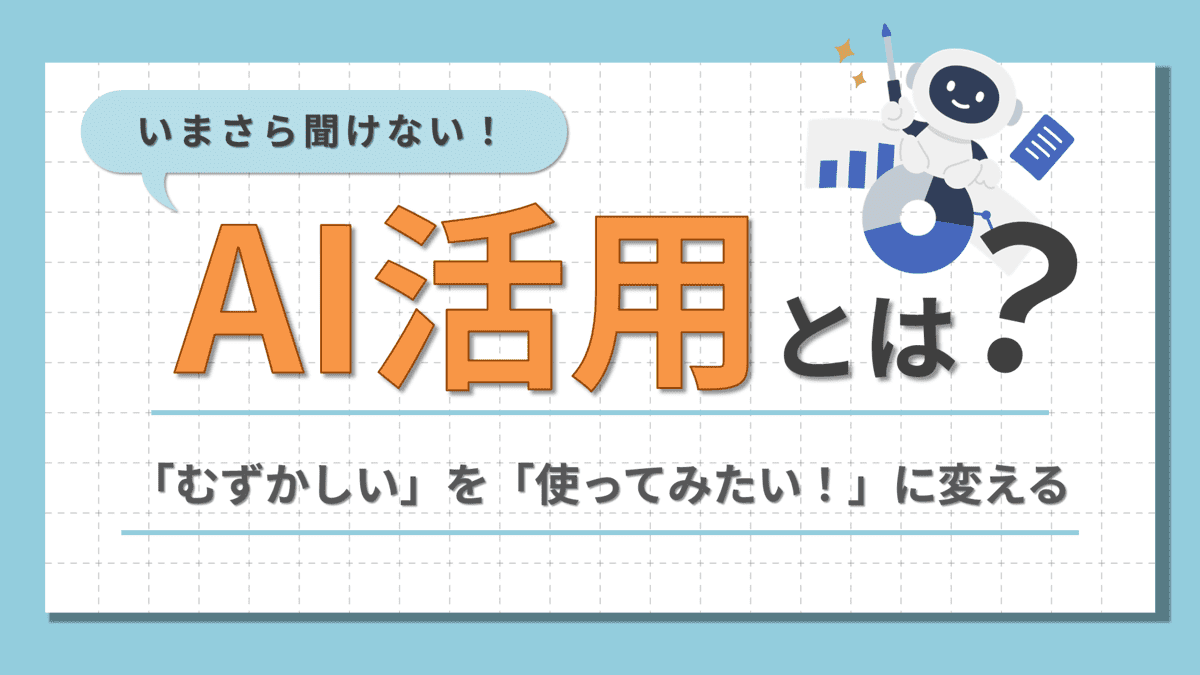
いまさら聞けない!AI活用とは?
企業の業務効率化や意思決定のサポートにおいて、AIの導入がますます重要になっています。AIの基本的な知識から、従来型AIと生成AIの違い、AIアシスタントの活用方法まで幅広くご紹介しています。
業務改善を継続するためのポイント
一度改善しただけで終わらせず、継続的に改善を進めるための考え方や組織づくりのコツを解説します。
業務改善は一過性のイベントではなく、組織文化として根付かせることが肝要です。定期的に進捗を確認し、問題が再発していないかや新たな課題が生じていないかをモニタリングし続けましょう。
従業員の自主性を尊重し、意見を吸い上げる仕組み作りも欠かせません。現場からの改善提案を取り入れやすい環境を整えることで、次々と新しい発想が生まれ、業務改善が加速します。
また、改善の成果を適切に評価・報酬に反映する制度を整えておくと、メンバーのモチベーションが高まり、持続的な取り組みへと繋げることができます。
業務改善の成功事例
ここではグループウェア desknet's NEO、ノーコード開発ツール AppSuiteの利用して業務改善に成功した事例を紹介します。
業務の属人化解消と自動化による負担軽減
塗料・化学製品を扱うナトコ株式会社では、経理・総務業務が属人化しており、担当者の負担が大きくなっていました。そこでdesknet's NEOとAppSuiteを導入し、業務フローを見直しながら申請・承認・集計などのプロセスを自動化。これにより、情報の一元管理が可能となり、業務の抜け漏れや手戻りが大幅に減少しました。担当者の負担軽減だけでなく、社内全体の生産性向上にもつながった好事例です。ITに詳しくなくても、現場主導で改善できる点が多くの企業にとって参考になります。
ポータル再構築による社内情報共有の活性化
静岡県の老舗食品メーカー・株式会社いちまるでは、社内ポータルの利用率が低下し、情報共有が形骸化していました。そこでdesknet's NEOを活用し、ポータルの構成やデザインを一から見直し。「思わず開きたくなる」ポータルを目指して、社員の目線に立った情報配置や更新頻度の工夫を行いました。その結果、社内の情報流通が活性化し、部署間の連携もスムーズに。グループウェアの再設計によって、社内DXの基盤を整えた事例として、既に導入済みの企業にも大きなヒントを与えてくれます。
業務のムダの見える化と情報共有の効率化
鹿児島県内のJAグループでは、他社製品のサポート終了をきっかけにdesknet's NEOを導入。業務の流れや情報のやり取りに潜むムダを洗い出し、「見える化」することで、改善の余地を明確にしました。特に、紙ベースで行われていた申請や報告業務を電子化することで、情報共有のスピードと正確性が向上。複数の部署が関わる業務でも、リアルタイムで状況を把握できるようになり、組織全体の連携力が強化されました。大規模組織でも業務改善は可能であることを示す、実践的な事例です。
避難計画業務のシステム化による作業時間削減
横浜市役所では、災害時の避難計画業務が紙とExcelで管理されており、作業負担が大きく、情報の更新にも時間がかかっていました。desknet's NEOを導入し、避難計画の作成・管理をシステム化することで、作業時間を約41%削減。職員の業務負担を軽減しながら、災害対応力の向上にもつながりました。自治体という公共性の高い組織でも、業務改善によって効率と品質を両立できることを示す好例です。紙業務の多い組織にとって、デジタル化の第一歩として非常に参考になります。
社内データ×最新のAI技術で様々な業務に特化したAI社員をスピード構築
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
まとめ
ここまで紹介した業務改善のポイントを整理し、今後の取り組みに役立つ視点を振り返ります。
ここまでの流れを振り返ると、業務改善ではまず現状をしっかりと可視化し、課題を整理することが大きな第一歩となると分かります。そこから改善案を検討し、実行計画へとつなげていくプロセスを確立すれば、確実に組織全体が効率的に動くようになります。
重要なのは、改善後の振り返りと継続的な見直しです。新しい課題が発生する可能性は常にあり、その都度PDCAサイクルを回して最新の状況に合わせた改善策を実行することが理想的です。
組織文化として業務改善マインドが根付けば、社員個人はもちろん、企業全体の生産性や競争力が飛躍的に高まるでしょう。前向きに改善へ挑戦し、新たな価値を生み出す力を組織で育んでいくことが大切です。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
業務改善についてもっと詳しく

desknet's NEO ユーザー事例集
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOを活用し業務改善に成功したお客様の導入事例を集めました。
更新日:
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221


 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部