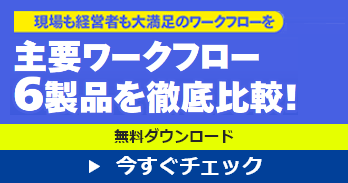稟議書の書き方とは?
例文とテンプレート、承認を得る5つのコツを紹介

稟議は関係者の承認を得る重要な手続きのひとつです。「稟議書」というと非効率的なイメージがありますが、うまく取り入れることで逆に承認や決裁を効率化するなど、いくつものメリットが得られます。しかし、作成した稟議書が的外れだったり、処理に時間がかかったりすると、かえって非効率的になるものです。
また、最近はテレワークが普及し、一般に紙の書類でのやり取りは好まれません。稟議書も、時代に合わせて手法を変える必要があるでしょう。
ここでは、稟議書の概要とメリット・デメリット、承認を得るための書き方のポイントから、処理を効率化する方法までをご紹介します。
ペーパーレスについてのおすすめ資料

稟議書の目的と機能
稟議とは?稟議書とは?
稟議とは、組織での活動において、個人の権限だけで決定できない事柄が発生した際に、書面によって関係者や上司へ回覧し、承認・決裁を得るための手続きのことです。「稟議申請」「社内稟議」などとも呼ばれます。
例えば、業務で使用する備品を購入したいとき、新しい取引先と契約をしたいとき、従業員を採用したいときなど様々なケースがあります。その稟議を申請するための書面を「稟議書」と呼びます。
稟議書と決裁書の違い
稟議書
承認を得たい案件について、書面の形で承認を依頼することです。複数人の間で順番に書類が回覧され、全員に承認されなければなりません。 最初に書類を提出する(稟議を上げる)のは申請者で、最後は最終決定を行う管理職です。最終決定者が承認することは「決裁」と呼ばれます。 複数の部署が関係する場合は、一般的に稟議が必要です。そのため、決定までに時間がかかります。
決裁書
権限のある役職者が、重要な事項を、内容を確認してから直接承認することです。稟議の最終決定も決裁と呼ばれます。 最終決定者は一人です。複数名による検討や確認を行うわけではないため、判断ミスや書類の不備の見落としが起こることもあります。
稟議書と起案書の違い
稟議書は上記の通りですが、起案書は業務を遂行するうえで関係者の承認を得ることが必要な事案がある場合に、その事案を文書としてまとめることを指します。稟議書の作成も、起案に含まれます。
稟議書を作成するメリット
稟議書の作成には、次のようなメリットがあります。
承認者が内容を把握・検討しやすい
案件の目的や理由、必要経費、メリットなどを具体的かつ簡潔にまとめた稟議書があれば、審査する側も内容を容易に把握し、検討しやすくなります。
不要な会議が減る
稟議書を活用すれば、審議する側も文書1枚で内容を理解し、可否を判断できます。その分、内容説明・審議の会議を減らすことが可能です。
業務取り掛かりまでのスピードが短縮される
稟議書で業務内容があらかじめ確認されるので、承認されれば最小限の打ち合わせで迅速に業務に取り組むことができます。
情報共有しやすく、トラブルやミスなどの防止につながる
稟議書を作成・共有することで、スムーズに情報共有ができます。何人もの目で確認することで、見落としていたミスや問題を発見し、トラブルを防ぐことも可能です。
組織的に管理できる
稟議書を関係する部署にも回すことで、どの部署でどのような活動をしているかを把握しやすくなり、案件の進行を組織的に管理できます。
ワークフローについてのおすすめ資料

主要ワークフロー6製品を徹底比較
数あるワークフロー製品の中から、All in one型のワークフロー3製品と特に認知度の高いワークフロー専用ツール3製品を機能面・コスト面から徹底比較した資料です。
稟議書を作成するデメリット
稟議書の作成に伴うのは、メリットだけではありません。場合によっては、次のようなデメリットもあります。
権限者が不在の場合、最終承認を受けるまでに時間がかかる
稟議書は複数人の承認が必要です。そのため承認者のうち誰かが不在の場合、待ち時間が生じ最終承認までに時間がかかることがあります。
トラブル発生時の責任の所在を問いづらくなる
複数の人間が承認するため、トラブルが発生したときに責任の所在がわかりづらくなります。
承認を得やすい稟議書の書き方 5つのコツ

決裁者が内容を理解しやすく、速やかに審査・承認されるような稟議書を作成するには、次のようなポイントを押さえる必要があります。すでにフォーマットがある企業でもこれらを意識することで、より精査しやすい稟議書になるでしょう。
必要な情報を簡潔に記入する
一読して内容を理解できるよう、簡潔に分かりやすく書きましょう。相手が情報を簡単に理解して精査しやすくなるよう、冗長な表現を避け、明確に伝わるよう記載します。 箇条書きや番号をうまく利用すると内容を整理しやすくなります。他の部署に回すことも考え、専門用語を入れすぎないことも重要です。
稟議にかけるに至った背景も記載
簡潔な表現を心がけることは重要ですが、承認者が申請内容について詳しくない可能性があります。申請に至った背景や事情があれば記入します。
リスクや注意点にも触れる
稟議書にはメリットや効果だけを記載してしまいがちです。しかし、承認する側にとってはリスクや注意点も「知るべき情報」となります。懸念点も正確かつ客観的な視点で記載します。
関連資料も添付する
契約に関する書類、備品購入に関する場合は見積書など、必要に応じて書類を添付しましょう。公的な統計データや競合他社の状況など、承認の判断をするために必要な資料があれば、準備して添付します。その際、数字は正確なものを使用する必要があるので、信頼性の高いソースのデータを用いるようにしましょう。
伝えきれない情報は、事前に共有する
稟議書をいきなり申請するのではなく、事前に決裁権者や承認者に、内容を伝えておくことも承認を得るためには有効な手法です。いわゆる「根回し」です。決裁権者や承認者は、あらかじめ内容を知ることで心の準備ができ、安心して稟議書に目を通すことができるようになります。事前にアドバイスをもらうのもよいでしょう。
これらのポイントを社内で周知することによって、手戻りの少ない稟議書が作成されやすくなります。そのほかにも、過去の稟議書を参考にするというやり方もあります。過去に承認が下りた稟議書を可能な範囲で参考にすることで、差し戻しを減らし、より通りやすい稟議書を書くことができるでしょう。
前述したポイントを押さえても手戻りが多い場合は、フォーマットの内容が実態に合っていない可能性があります。フォーマットの内容を一度見直してみることをおすすめします。
業務改善についてもっと詳しく

desknet's NEO ユーザー事例集
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOを活用し業務改善に成功したお客様の導入事例を集めました。
稟議書の例文・テンプレート
ここでは、稟議書に掲載するべき稟議書の記入項目を紹介します。
一般的な稟議書の項目
一般的な稟議書には、次のような項目を記載します。
- 申請の日付:申請を行う日付を記入します
- 起案者:起案者の部署名と本人の氏名を記入します
- 起案番号:企業ごとの規定に基づいた番号です。決裁番号と呼ばれることもあります
- 件名・タイトル:稟議の内容がを明確に、簡潔に記入します
- 稟議の内容:稟議の目的・効果・理由などメインとなる事項を記入します
- 承認者のコメント欄・承認欄:決裁者からの意見や疑問点が生じた際に記入する欄です
- 添付書類、資料:契約書や見積書、履歴書・職務経歴書など、承認の判断に必要な書類があれば添付します
稟議書の目的に応じたフォーマットを作成
一般的な内容は既述のとおりですが、それ以外に目的ごとの微調整も必要です。フォーマットは目的に合わせて何種類か紹介していますので、稟議書を作成する際の参考にしてください。
購買稟議書
社内で使用する備品の購入をする際の稟議書です。主な項目は次のとおりです。
| 起案日 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |
|---|---|
| 決裁日 | 〇〇年〇〇月△△日 |
| 起案者部署 | 営業部 |
| 起案者 | 山田 太郎 |
| 起案番号 | NO.XXYYYZZ |
| 件名 | ノートパソコン購入の件 |
| 品名 | XXX社ノートパソコン PC-XXX500 |
| 数量・金額 | 99,800円 1台 |
| 起案理由 | 現在使用中のノートパソコンが故障しました。メーカーの修理センターからも修復は不可能との回答があり、新たに購入をいたします。 |
| 発注先 | □□電機株式会社 |
| 支払日 | 〇〇年〇〇月▽▽日 |
| 条件付き承認/否認の理由 |
設備導入稟議書
社内で使用する設備を導入する際の稟議書については、記入のポイントは次のとおりです。
- 設備名のほか、導入目的とどのように導入するのかといった概要を記載する
- 費用(総額だけでなく価格・工事費・導入費などの金額の内訳も記載する)
- 既存設備との違い、設備投資することによってもたらされる効果などを記載する
人事採用稟議書
採用を行う際の稟議書です。採用(予定)者の人数や給与、配属先などについて伝えることで、適切な採用を行っているか判断を仰ぎます。記入のポイントは次のとおりです。
- 希望採用人数(比較として本年度の採用者数を記載する項目があってもよい)
- 給与・配属先といった人員計画
- 採用の理由(欠員が発生している、業務範囲の拡大予定など妥当性を感じられる理由が望ましい)
- 必要性に応じて職務経歴や資格などの採用(予定)者情報
広告出稿稟議書
広告出稿に関する稟議書の記入のポイントは次のとおりです。
- 対象となる商品やサービス、広告出稿する目的などの概要
- 広告出稿予算
- 掲載時期と掲載先
- 出稿によって見込める売り上げ・認知度アップなどの効果
このように、よく使われる種類の稟議書については目的に応じたフォーマットを準備しておくことをおすすめします。 しかし、すべてのフォーマットを準備するのは難しいでしょう。申請の頻度が低いものや、項目にバラつきがあってフォーマット化しにくいものについては、汎用性のある一般的な内容の申請書で対応するといったように、使い分けます。
稟議に関する課題はワークフローシステムで解決
以前は、稟議書を紙に印刷して押印したのち承認者へ提出する、または稟議書をメールに添付して申請する、といった流れが主流でした。現在はSaaSで利用できるワークフロー専用システムやグループウェア(多数の機能の中にワークフロー機能を装備)を利用する場合がよくみられます。社内の効率的な稟議・申請業務を進めるためには、迅速にミスなく進めやすいワークフローシステムの利用は不可欠です。
よくある稟議書の課題
稟議書の申請の際には、以下のような課題が発生しがちです。
作成・承認に時間がかかる
案件を稟議にかける場合、基本的には起案者が紙の書面を作成し、最終決定者に至るまでに数人の承認を経て決裁、つまり最終決定がなされます。この過程にはある程度の時間がかかります。
また、申請のたびにゼロから稟議書を書くにも時間が必要です。
紙の書類は非効率的
紙の稟議書では、承認の有無ははんこによって確認するのが一般的です。そのため、書面の物理的な受け渡しが欠かせません。最近では業務のデジタル化、ペーパーレス化やテレワークの促進によって、紙の書類が前提の稟議制度は業務実態にそぐわないという考え方も出てきています。
フォーマットが異なると非効率的
起案者ごとにフォーマットや内容が異なると承認者も内容を検討しにくいものです。
そのため社内でフォーマットを作成し、それをもとに稟議書を作成するのが望ましいとされています。
手戻りが多い
順調に承認がされていても、最終決定者が不可とすれば決裁されることはありません。作成者に戻ってきます。
また、必要な情報が網羅されていなければ最終決定者に至る前に手戻りがあります。不備の修正や申請内容のブラッシュアップを行わなくてはなりません。
ワークフローの電子化は申請・承認を効率化するための近道
ワークフローを電子化することは、上記のような課題解決に大いに役立ちますが、特筆すべきメリットには以下の3つが挙げられます。
- 意思決定のスピードアップ
- 稟議作成の効率化・検索性の向上
- 社外からも決裁ができるようになる
電子化することで、PCやタブレット、スマートフォンから、社内・外出先といった場所を問わず稟議に関する業務を進められるという点も、稟議のスピードアップという点でメリットとなるでしょう。ここ数年で広がったテレワークなど、場所を問わない多様な働き方にも対応することができます。以前提出した申請データは蓄積され、それらを参考にすることでより読みやすく理解しやすい、承認を得やすい稟議書をの作成にもつながります。
社内の稟議用にフォーマットを作成しても、最新の書式が共有されないと意味がありません。最新ではないフォーマットで稟議書を書く社員が存在すれば、手戻りが発生し、業務が滞るでしょう。また、フォーマットは整えたとしても、承認ルートが複雑で申請先に間違いがあると、そこでまた手戻りが発生してしまうといったパターンもあります。
稟議制度においては、単純に紙の書類をデジタル化するという利点よりも、個人に依存した書式や経路を使うという非効率な面を解決するという利点の方が大きいと言えます。
また、システムによっては、フォーマットごとに申請経路を紐づけられたり、代理承認、自動承認機能など、より効率化に役立つ機能が付加されているものもあります。
ワークフロー管理の重要性とは?業務の具体例やシステムの選び方も解説
ワークフローシステム導入のメリット
稟議書のフォーマットが統一される
ワークフローシステムには、目的に応じて豊富なテンプレートが用意されていることが多いので便利です。システム上において最新フォーマットを登録することで、過去のフォーマットを使ったり古い経路を設定してしまうというミスを避けられます。また、入力項目が統一されることで、記入の抜け、漏れといった手戻りも減り、スムーズに業務が進みやすくなるでしょう。
業務フローに合わせてカスタマイズ!申請・承認の効率化が進むワークフローアプリとは
承認の進捗が可視化される
ワークフローシステムでは、書式ごとにあらかじめ経路を設定することができます。一承認者による承認が下りると、自動的に次の承認者に申請書が送られます。ワークフローシステムを利用することで、承認ルートの間違いをなくし、承認ルートを毎回確認し設定する手間を省くことができます。また申請書が承認ルートのどの段階にあるのか確認することも可能です。
テレワークでも稟議申請が進められる
物理的な紙の稟議書ではなく電子文書になるため、出社する必要がありません。テレワークでも問題なく稟議を進めることができます。
稟議申請の情報管理や稟議書の保管が容易になる
データとして情報を蓄積できるため、稟議書の紛失が防止できます。紙のvファイリングのように保管に場所を取ったりすることもありませんし、過去の稟議書を見返したいときも検索がしやすく見つけやすいこともシステム利用の良い点です。
このように、ワークフローシステムを導入すれば、申請者・承認者ともに稟議に関わる業務負担を減らすことができます。
ワークフローの電子化にはグループウェアも有効
稟議書の電子化は、ワークフロー専用のサービスもありますが、さまざまな機能を備えたグループウェアを導入することも有効です。グループウェアならば、稟議以外にも社内情報の発信・共有、スケジュール管理といった機能も標準装備されており、それぞれの機能を連携させることもできます。チャットや業務アプリ作成ツールも連携できるなど、さらなる業務の効率化・生産性の向上が期待できます。
稟議は電子承認システム「ワークフロー」の導入でスムーズに!
ワークフローの選び方についてのおすすめ資料

主要ワークフロー6製品を徹底比較
数あるワークフロー製品の中から、All in one型のワークフロー3製品と特に認知度の高いワークフロー専用ツール3製品を機能面・コスト面から徹底比較した資料です。
ワークフローの電子化はdesknet's NEOがおすすめ
グループウェアdesknet's NEOには、ワークフロー機能をはじめ、ビジネスに役立つ27もの機能を標準で備えています。
チームでの業務を円滑に進めるには、グループウェアの中でも豊富な機能とUIの見やすさ、操作性において定評のある「desknet's NEO」が特におすすめです。業種問わず、会社や官公庁、団体で広く利用されています。組み合わせて使うとより便利なノーコードのアプリ作成ツールやビジネス向けチャットもオプション提供。パソコンのほかスマートフォン、タブレットでも利用できるため、いつでもどこででも、効率よく仕事を進めることができます。
こちらの動画では、先にご紹介したdesknet's NEOのワークフロー機能を詳しくご紹介しています。ぜひごらんください。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
稟議書の書き方に関するまとめ
本記事では、稟議書の書き方、承認を得やすくするための書き方のコツ、稟議承認業務の電子化のメリットについて紹介しました。 稟議申請にワークフローシステムを導入することで、承認ルートや進捗状況が可視化でき、稟議申請の運用管理がぐっと容易になります。稟議書のデジタル化を行う際には、ワークフロー全体をデジタル化するワークフロー専用システムのほか、グループウェアの利用も選択肢としておすすめします。専用システムにはない、いくつものメリットを得られるでしょう。 特に、業務全体の効率化のためには、稟議以外にも使える機能がそろっていることが望ましいです。使い勝手や機能性を見極めたうえで、自社の生産性向上に貢献するツールを導入しましょう。
ただし、それまで使用してきた稟議書のフォーマットを大きく変えると現場の混乱を招きかねません。それまでの稟議書のイメージを再現できるようなツールを選ぶと、スムーズに移行できるでしょう。無料のトライアルができるサービスも多くありますので、実際の画面や操作しやすさ、使い勝手をしっかりと見極めてから導入をされることをおすすめします。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
デスクネッツ ネオについてもっと詳しく

desknet's NEO 製品カタログ
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOの製品ご案内資料です。
更新日:
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221


 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部