アルコールチェッカーの数値を正しく理解する方法

近年、飲酒運転対策としての取り組みが強化され、安全運転への意識がますます求められるようになりました。
企業におけるアルコールチェック義務化に伴い、社用車や営業車を持つ多くの企業で、アルコール濃度を測定する機会が増えています。
ここでは、アルコールチェッカーの数値の正しい見方やその重要性、飲酒にともなうリスクを幅広く取り上げて解説します。酒気帯び運転の基準値や酒酔い運転との違い、さらにそれぞれの罰則内容など、知っておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。
アルコールチェッカーの定期的な点検や使用時の注意点などもあわせて理解し、一人ひとりが安全運転を実践できるよう正しい知識と意識を身に付けることが大切です。
酒気帯び運転を判断するアルコールチェッカーの数値とは
まずは、どの数値以上で酒気帯び運転とみなされるのか、その目安と酒酔い運転との違いについて確認しましょう。
酒気帯び運転の基準値
酒気帯び運転の罰則対象となる基準値については、道路交通法施行令によって具体的に規定されています。
法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合に該当することが一般的な基準とされています。具体的には、わずかな酒量でも摂取したタイミングや個々の体質によってこの数値を超えることがあるため、飲んだ量ではなく実際の呼気測定値を基準にすることが重要です。
さらに、0.25mg/Lを超える濃度が検出された場合は、より重い罰則が科され、免許の停止や罰金の対象範囲が拡大します。企業や事業所では、この基準を考慮して従業員の飲酒運転のリスクを管理し、厳しい姿勢で対策を講じることが求められます。
酒酔い運転の基準値
酒酔い運転は、数値基準に加えて運転者の身体機能や判断力が著しく低下しているかどうかがポイントです。道路交通法 第百十七条の二では「酒酔い運転」を「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と規定しています。正常な運転ができなくなる程度に酔っていると判断されると、より重い行政処分や刑事罰が科される可能性があります。
つまり、数字としては大きくなくとも、運転が困難なほどの飲酒であれば酒酔い運転と見なされるのです。アルコールチェッカーの数値だけに頼らず、飲酒後は少しでも万全に運転できないと感じたらハンドルを握らない姿勢が重要です。
飲酒運転の罰則から企業の対処法・対策まで徹底解説
アルコールチェッカーの数値の見方
ビジネスシーンや業務での安全運転を推進する際に重要なのが、アルコールチェッカーで得られる数値の正しい理解です。市販されている多くのアルコールチェッカーは、呼気中のアルコール濃度を測定し、その結果を小数点以下二位または三位まで表示します。この数値をもとに、測定対象者が酒気帯び運転の罰則対象になるかどうかを判断します。法令で定められたアルコール濃度基準値を超えている場合には、法的措置が講じられる可能性があるため、正確な読み取りが求められます。
購入の際には、アルコールチェッカーの仕様や精度、そして検出限界についても十分に確認することが推奨されます。製品によりこれらの特性が異なることがあるため、用途に合ったものを選ぶことが重要です。
また、酒気帯び運転および酒酔い運転に関する基準値や罰則の内容について詳細を知りたい方は、以下の表をご覧ください。これにより、具体的な法令基準や罰則内容について理解を深め、安全運転の重要性を再認識する一助となるでしょう。
アルコールチェッカーの数値表
| 違反種別 | 呼気中アルコール濃度 | 違反点数 | 処分 | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
| 違反ではない | 0.15未満 | - | - | - |
| 酒気帯び運転 | 0.15以上 ~ 0.25未満 | 13点 | 免許停止(停止期間90日)※1 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 0.25mg以上 | 25点 | 免許取消(欠格期間2年)※1,2 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
| 酒酔い運転 | 数値基準なし 正常な運転ができない恐れがある状態 | 35点 | 免許取消(欠格期間3年)※1,2 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
※1: 前歴及びその他の累積点数がない場合
※2:欠格期間とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間
基準値を超えた運転に対する罰則
アルコールチェックで基準値を上回ったまま運転すると、どのような処罰が待っているのでしょうか。まず、酒気帯び運転の場合は罰金や免許取り消しなどの行政処分が科されやすく、さらに社会的信用を大きく損なうリスクを含みます。これが酒酔い運転にまで至ると、懲役刑などの厳しい刑罰が科される可能性も高まり、事後対応だけでは済まない深刻な問題となります。運転者はもちろんのこと、企業としても管理責任を問われるケースがあるため、常に基準値を意識し誤った判断を回避することが重要です。
特に企業で運送業や営業車を運用している場合、従業員が酒気帯び運転となると企業としての社会的信用を失いかねません。事故が発生すれば、被害者への補償や損害賠償にとどまらず、取引先や顧客からの信頼も失うリスクがあります。法的なペナルティだけでなく、企業イメージの悪化にも直結するため、アルコールチェックを徹底し、基準値を超えたら運転を中止するなどのルールを明確にしておくことが求められます。
酒気帯び運転の罰則

酒気帯び運転に該当する場合、まずは免許停止や罰金刑が主な罰則として挙げられます。呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上0.25mg/L未満の場合でも高額な罰金が科される可能性があり、運転免許の停止期間も長期に及ぶことがあるため注意が必要です。企業の運転業務に従事する人であれば、業務継続が難しくなるだけでなく、企業側にも管理責任が及ぶ点を忘れてはいけません。たとえ少しの飲酒でも数値が0.15mg/L以上となれば罰則適用になるため、前日の飲酒量にも十分気を配る必要があります。
酒酔い運転の罰則
酒酔い運転は、アルコールの影響で正常な運転ができない状態と見なされるので、酒気帯び運転よりも重い罰則が科されやすいです。たとえば、罰金の額や懲役の長さも厳しく設定されており、一度の違反であっても大きなダメージを受ける場合があります。業務中に酒酔い運転をした場合は、企業全体の信用失墜につながるうえ、顧客や取引先にも不安を与えてしまうでしょう。酒酔い運転を発生させないためには、運転者自身の責任感と、企業の管理体制が密接に連携することが大切です。
酒類提供者や同乗者が受ける可能性のある罰則
飲酒運転を助長したとみなされるケースで適用される罰則について説明します。
飲酒運転の罰則は運転者に限りません。酒類を提供したり、運転者が飲酒していると知りながら同乗したりした場合にも、厳しい罰則が科される可能性があります。こうした行為は、間接的に飲酒運転を助長したと判断されるため、法律上の責任が問われる仕組みです。同乗者や酒類提供者がいる環境での飲酒運転は、その周囲の人々も運転を止める義務を果たさなかったとして責任を負う可能性があることを認識しておく必要があります。
飲酒運転の罰則から企業の対処法・対策まで徹底解説
従業員が飲酒運転をした企業への罰則
従業員が飲酒運転で逮捕されたり事故を起こしたりすると、企業にも管理責任に基づく行政処分や罰金が科される場合があります。特に、安全運転管理者を置く必要がある事業所では、チェック・指導の十分性が問われ、管理不備が認められると厳しい処分を受けることもあるでしょう。さらに、社会的な信頼低下は取引先や顧客への影響にとどまらず、人材採用や企業イメージにも大きな打撃をもたらします。
こうしたリスクを回避するためには、アルコールチェックの徹底と安全運転教育の強化が鍵となります。少しでも飲酒の兆候がある従業員に適切な措置を講じ、ルールを破った場合には厳正な対応を取る姿勢を明らかにしておくことが重要です。企業が高い意識を持って取り組むことにより、安心して働ける環境づくりと事故の未然防止が期待できます。
安全運転管理者とは?選任が必要な場合と主な業務
2023年12月にアルコールチェックが義務化された内容とは
2023年12月からの法改正により新たに義務化された点を押さえましょう。
2023年12月から始まったアルコールチェック義務化の背景には、飲酒運転による交通事故の深刻化があります。特に、営業車両を使用する事業所や運送業者では、既存のチェック体制だけでなく、対面や遠隔での確認を積極的に行い、より確実に飲酒の有無を把握する必要が生じました。各企業ではアルコールチェッカーの整備や定期的な校正、さらには測定結果の保存を徹底することが法的に求められています。
アルコールチェック義務化に伴い、企業が行うべき対応とは?
アルコールチェッカーの正しい使い方
正確な測定値を得るためのアルコールチェッカー利用時のポイントをお伝えします。
アルコールチェッカーで正しい数値を測定するには、使用方法やタイミング、環境条件などに気を配る必要があります。測定センサーの感度が下がっていないか、吹き込み方や時間を守っているかといった基本事項を徹底することで、誤った結果を防ぎやすくなります。特に業務用として導入する場合は、多数の従業員が同時に使用するケースもあるため、機器のメンテナンスや利用ルールの統一化が欠かせません。正しい使用方法を社内で周知徹底し、導入後も定期的に確認する習慣を持ちましょう。
対面でのチェックの重要性
アルコール項目の確認は、可能な限り安全運転管理者や責任者が対面で行うのが理想的です。直接顔を合わせて測定することで、テストを実施しているかどうかの確認を確実に行えます。さらに、機器が正しく動作しているかや吹き込みが適切かどうかをその場でチェックできるため、不正や測定漏れの防止にも役立ちます。こうした対面チェックを日常的に実施することが、企業としてのコンプライアンスと安全意識の向上につながります。
リモートでのアルコールチェック方法
一方で、遠隔地に多数のドライバーを抱える企業においては、物理的に対面での測定が難しい場合があります。このような場合には、ビデオ通話や電話を利用してアルコールチェッカーの数値を確認する仕組みが効果的です。リアルタイムでの映像や音声を通じて、ドライバーが正しく機器を操作しているかを管理者が確認することで、不正防止や測定漏れを抑えることができます。特に広範囲の地域をカバーする運送業界では、このリモート手法が安全管理上で大きな役割を果たします。
前日の飲酒を避けるべき理由
アルコールの代謝には個人差があり、前夜の飲酒量や時間帯によっては翌朝になっても体内にアルコールが残っている可能性があります。特に体調が悪い時や睡眠不足の状態だと、アルコールの分解が遅れやすくなるため注意が必要です。朝起きてすぐにアルコールチェッカーを使った際に数値が残っていれば、運転を控える決断を迫られます。企業としても、前日の過度な飲酒をしないよう従業員への注意喚起を徹底しておくことが事故防止に役立ちます。
アルコールチェッカーのタイプによって測定精度が異なる
アルコールチェッカーには主に電気化学式と半導体式の2種類があり、電気化学式のほうが精度の高い測定が期待できるとされています。一方、半導体式は価格が比較的安価で取り入れやすいものの、温度や湿度の影響を受けやすく誤差が出やすい面があります。企業で導入する際には、コスト面だけでなく運用シーンに合った精度が確保できるかを考慮することが大切です。最適な種類を選択することで、誤検知や見逃しを減らし、正しい数値を確認できます。
故障時に生じる誤数値のリスク
アルコールチェッカーも機器である以上、センサーの老朽化や汚れによって故障が生じる場合があります。頻繁に使っているうちに精度が落ちたり、落下や衝撃で内部パーツが損傷したりすると誤った数値が表示されやすくなります。そこで定期的な点検やキャリブレーションを行い、異常を早期発見してメンテナンスすることが重要です。故障したまま使用を続けると管理体制自体に不備があるとみなされ、企業に不信感を与えるリスクにもつながります。
アルコール含有薬品への注意
胃腸薬や風邪薬、うがい薬など、日常的に使用する薬剤にもアルコールが含まれるものがあります。これらの薬品を服用後すぐにアルコールチェックを行うと、あたかも飲酒したかのように数値が上がることもあり得ます。こうした場合は時間をおいて複数回測定するなどの対策を取り、誤結果を排除することが大切です。薬品使用前後のタイミングを正確に理解することで、混乱や不必要な運転制限を避けられます。
周囲環境がもたらす影響
アルコールチェッカーを使用する環境によって、測定結果が変化する場合があります。たとえば、車内に消毒用アルコールを噴霧していると、その空気を吸い込むことでセンサーが反応してしまうことがあるのです。高温多湿の環境でも測定誤差が増大しやすいため、なるべく室内の空調や換気に配慮して測定するのがおすすめです。周辺環境を整えるだけで、より信頼性の高い測定結果が得られます。
薬服用のタイミングを考慮
風邪薬や鎮痛剤など、アルコールが含まれている可能性のある薬を服用するタイミングは、アルコールチェックの結果に影響を与えます。服用直後の状態では数値が高く出る場合があるため、服用後は少し時間を置いてから検査するなど工夫が必要です。とくに業務の開始直前に薬を飲む場合は、誤った数値によって出勤停止などの措置が取られないよう、事前に管理者に相談することが望ましいです。安全運転を優先しながら、適切な服用と測定のバランスをとりましょう。
飲酒せずとも反応する可能性のある食品と対処法
なぜアルコール反応が出るのか?
アルコールチェッカーは非常に感度が高いため、飲酒していなくても、特定の食品や口腔ケア用品が原因でアルコールが検出されることがあります。これはチェッカーの故障ではなく、食品等に含まれる微量のアルコール成分に反応するためです。
パンや味噌、漬物などの発酵食品は、製造過程の発酵により微量のアルコールが生成されることがあります。そのため、例えばあんパンや洋酒入りのチョコレートなどを食べた直後に測定すると、口腔内に残った成分にチェッカーが反応してしまう場合があります。
誤検知が疑われる場合の対処法
もし飲酒の心当たりがないのにアルコールが検出された場合は、慌てずに以下の対応を取りましょう。アルコール検知器協議会も同様の対応を推奨しています。
水でうがいをする
まず口の中を水でよくすすぎ、口腔内に残った食品や液体の成分を洗い流します。少し時間をおいてから再測定する
うがい後、数分から10分程度の時間を空けてから再度測定します。口腔内の残留物が原因であれば、再測定によって数値が0.00mg/Lになるか、大幅に下がります。
警察の取り締まりで誤って摘発されることはある?
「もし検問でパンを食べた直後だったら…」と不安に思う方もいるかもしれません。
この点について、警察の取り締まりは、単に検知器の数値だけで機械的に判断されるわけではないようです。報道などによれば、実際の現場では運転者の呼気の臭いや顔色、言動、まっすぐ歩けるかといった総合的な状態で判断されるとされています。
万が一、検知器が反応した場合でも、すぐに違反として処理するわけではありません。飲酒の疑いがあれば、水でのうがいを促した上で再測定を行うなど、慎重な捜査が行われています。そのため、「マウスウォッシュを使っただけ」といった虚偽の申告は通用しない一方で、本当に飲酒していない人が誤って摘発される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
しかし、企業におけるアルコールチェックでは、たとえ基準値未満であってもアルコールが検出された場合は運転を許可しないのが安全管理の原則です。測定前にアルコール反応が出やすい食品の摂取を避けるなど、ドライバー一人ひとりの意識も重要となります。
アルコール検出時の対応策
アルコールチェッカーを用いて測定を行った際、アルコールが検知された場合にはどのように対応すべきでしょうか。
飲酒していないのに、誤検知でアルコールが検出された場合
もし飲酒をしていないにもかかわらずアルコールチェッカーで数値が出た場合は、まず再度測定を行い経過観察をすることが重要です。先ほど述べた発酵食品や外部環境、機器のトラブルなどが原因となり、一時的に誤った数値を示すケースは少なくありません。再測定を行っても数値が下がらない場合は、体内にアルコールが残っている可能性を疑う必要があります。原因を特定できないときは、医師に相談するなど第三者の専門家によるチェックを受けることも選択肢の一つです。
運転前にアルコールが検出された場合
運転前の確認でアルコールが検出された場合、当然ながらその人に運転を許可することはできません。車を利用しない通勤方法を選択している場合には問題ありませんが、車を使用して通勤する予定であれば、それは飲酒運転となるため、最寄りの警察署などに通報が必要です。
運転後にアルコールが検出された場合
運転後の確認でアルコールが検出された場合は、運転中にアルコールを摂取した可能性が考えられます。同様に、警察署などに通報してください。その際、対応した内容を正確に記録に残しておくことが重要です。
安全運転管理者不在時のアルコール検出
安全運転管理者が不在の際に代理人がアルコールチェックを行い、アルコールが検出された場合は、速やかに安全運転管理者に報告しましょう。その後、必要な指示を仰ぎ、安全運転管理者から直接運転中止の指示を行うなど、安全運転を確保するために適切な対応を実施してください。
酒気帯び運転の基準を下回るものの、検出されたアルコール値が0より大きい場合の対応策
アルコール濃度が0.15 mg/L未満であっても0ではない場合、どのように対処すべきでしょうか。ここでは、その具体的な対応方法について説明します。
1.まずはうがいをして再測定を行う
直前に飲食、喫煙、あるいはアルコールを含む洗口液を使用した場合、アルコールチェッカーが誤って反応する可能性があります。このような心当たりがある方は、まずうがいをして一定時間を置いた後、改めて測定を行ってください。
2.再測定しても0にならない場合
うがいをしても再測定でアルコール値が0にならない場合は、たとえその値が酒気帯び運転の罰則対象基準を下回っていたとしても、運転は避けるべきです。アルコールが体内に残っているという状況は、交通事故のリスクを高めます。交通事故は人命に関わる重大な問題ですので、安全を確保するためにはアルコールが完全に体外に排出されるのを待つことが重要です。
なお、千葉県安全運転管理協会が作成した「アルコールチェック義務化Q&A」には、法定基準を下回るアルコール濃度でも運転を許可しないことが記されています。さらに、千葉県警察の記録においては、0.10 mg/Lを酒気帯びと見なす例もあります。詳細な情報や具体的なガイドラインについては、以下のリンクをご確認ください。
アルコールチェックの義務化と記録Q&A(千葉県安全運転管理協会).pdf
アルコールチェッカーの点検・メンテナンスに関する重要性について
道路交通法では、アルコールチェッカーを常に使用可能な状態で保持することが求められています。そのためには、こまめに点検やメンテナンスを行うことが非常に重要です。以下に、その具体的な方法をご紹介いたします。
日常点検の方法
日常点検は、毎日の使用前点検と週に1回以上の精度確認点検の2種類があります。
毎日の使用前点検:
- ・電源が正常に入ることを確認する
- ・装置に損傷がないことを確認する
週に1回以上の精度確認:
- ・アルコールチェッカーが正確に酒気帯びの有無を検知できることを確認する
精度確認の手順としては、次のような方法があります。
手順1: 酒気を帯びていない人物に水で口をゆすいでもらい、2~3分待ってからアルコールチェッカーで測定し、結果が0となることを確認する。
手順2: 同じ人物が再度水で口をゆすいだ後に、アルコールを含む洗口液を数プッシュ口にスプレーし、すぐにアルコールチェッカーで測定してアルコールを検知することを確認する。
これらの方法を用いて、日常の点検を実施してください。
アルコールチェッカーのメンテナンス方法
アルコールチェッカーのセンサー部分は、使用に伴って徐々に劣化するため、使用頻度や耐用年数が設けられています。これらの基準を超えた場合には、通常の点検とは異なり、センサー交換のためのメンテナンスが必要です。
一般に、アルコールチェッカーのメンテナンスは製造元への依頼が推奨されますが、一部の機種ではセンサーの交換作業を自身で行うことも可能です。その際は、取扱説明書などを参考に、交換方法を確認しておきましょう。
多くの機種では、使用回数や残り可能回数が本体に表示されたり、センサー交換時期を知らせるメールが届く仕組みがあるため、メンテナンスのタイミングを適切に把握できます。安心・安全のために、余裕を持ってメンテナンスを計画的に行うことをお勧めします。
一方、センサーが交換できないタイプの場合、本体ごとの買い替えが必要となるため、これも考慮に入れておきましょう。
アルコールチェッカーが正常に機能しないと、飲酒運転のリスクを生じさせる可能性があります。したがって、定期的な点検とメンテナンスの実施を忘れずに行うよう心掛けてください。
アルコールチェックの課題とその解決策:
業務効率化に貢献するアルコールチェックアプリ
アルコールチェックの義務化に伴い、多くの企業では担当者の負担増やドライバーの非協力的な態度など、さまざまな課題に直面する可能性があります。これらの問題を放置すると、せっかく導入したアルコールチェックが形骸化しかねません。そのため、事前に想定されるリスクを洗い出し、適切な対応策を準備しておくことが重要です。
業務負担の軽減策として注目されているのが、アルコールチェックアプリです。このアプリを導入することで、企業は法令を遵守しながら、煩雑な運転記録やチェック結果を効率的に管理できます。これにより、記録漏れや改ざんのリスクを低減し、正確かつ迅速なデータ管理が実現します。
アルコールチェック体制をより実効性の高いものとするためには、導入後の定期的なフロー見直しと改善も不可欠です。アルコールチェックアプリの活用と継続的な運用改善を通じて、担当者の負担を軽減しつつ、より安全な運行体制の構築を目指しましょう。
アルコールチェックアプリのメリットと特長とは
アルコールチェックアプリとは
アルコールチェックアプリは、ドライバーのアルコール検査を効率的に管理するツールです。法令に準じて、検査結果を正確に記録し保存することが求められており、このアプリの利用が注目を集めています。このアプリには、検査結果の登録や管理者へのリアルタイム通知、データの自動保存など、さまざまな機能が備わっており、多様なニーズに対応できます。これにより、業務の負担が軽減され、法令の順守がスムーズに進められます。
また、アプリによっては、車両管理機能や運転日報アプリなどの追加機能と連携できるものもあります。運行管理全体を一元化するプラットフォームとして、大いに活用できる可能性があります。
運転日報とは?記載項目や保存期間、活用方法を徹底解説!
車両管理とは?メリットや導入方法についてわかりやすく解説
アルコールチェックアプリのメリット
アプリを導入することで、業務の効率化が進み、リアルタイムでのチェック結果の保存や確認が可能になります。自動保存機能を活用すれば、管理者は全ての記録を簡単に確認でき、手作業の記入漏れや誤入力を防ぎます。結果的に、業務の負担軽減とともに、正確かつ効率的な記録管理が実現します。
管理者のメリット
管理者にとっても、アルコールチェックアプリを導入することは大いに効率的です。業務が自動化され、これまでは手作業が必要だった管理業務が効率的に行えます。記録のデジタル化により、情報の検索や分析が迅速になるため、必要なデータを容易に取得可能です。データの正確性向上とコンプライアンス強化に役立ち、結果として、管理者の負担は大幅に軽減され、信頼性も向上します。
ドライバーのメリット
ドライバーにとっても、アルコールチェック記録アプリは非常に有益です。紙ベースの記録や手作業が不要となり、操作が簡便で効率的になります。これにより、記録漏れや誤記入を防ぎ、安全が確保されます。また、運転前後のプロセスが可視化されることで、ドライバー自身の安全意識が高まり、安全運転への意識向上が促されます。
まとめ
アルコールチェック義務化と正しい運用のポイントを振り返り、今後の対策を考えましょう。 アルコールチェックの数値の正確な理解は、飲酒運転を未然に防ぎ、企業や社会の安全を守るうえで欠かせない要素です。0.15mg/L以上での酒気帯び運転や、数値に関係なく異常な酔い方をする酒酔い運転は、いずれも大きな罰則や社会的信用の失墜を招くおそれがあります。企業は法改正に対応しながら、安全運転管理者を中心に適切なチェック体制を整え、教育を通じて従業員の意識を高める取り組みを継続することが大切です。常にアルコールチェッカーのメンテナンスや利用方法の見直しを行い、社内ルールと実践の両方から飲酒運転のリスクを低減していきましょう。
アルコールチェックはアプリで簡単に

アルコールチェック&運転日報のご紹介
現場の「あったらいいな」を叶える業務アプリ作成ツールAppSuiteでアルコールチェック&運転日報アプリがご利用いただけます。
アルコール測定記録の保存から、運転日報の管理、日常点検の記録など、社用車・公用車の運用に伴う管理負担をdesknet's NEOとAppSuiteを用いて効率化。
更新日:
「アルコールチェック」についてもっと読む
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221



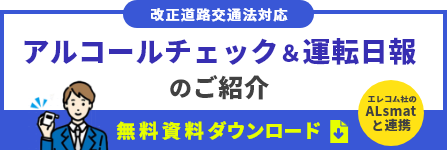
 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
