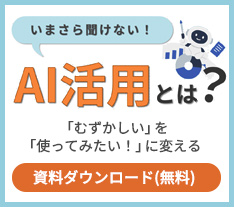ITリテラシーとは?
リテラシーを高める4つのメリットとその方法
ITの活用が日常業務のあらゆる場面で必要となる現代において、ITリテラシーは企業・個人問わず重要な能力となっています。ITリテラシーを高めることで、ビジネスの効率化やセキュリティリスクの低減など、多くのメリットが得られます。本記事では、ITリテラシーの基本や構成要素、重要性を解説するとともに、高めることによる4つのメリットと具体的かつ有効な方法をご紹介します。
ITリテラシーとは?
まずはITリテラシーの定義や背景を正しく理解することが大切です。
ITリテラシーとは、パソコンやインターネット、ネットワークなどのIT技術を正しく理解し、適切に活用するための能力を指します。近年はスマートフォンやSNSの利用が広がり、個人や企業での情報共有・活用の場面が増えています。これらの状況に対応し、セキュリティ対策や情報の信頼性を見極める力を持つことが重要になっています。
ITリテラシーの基本的な理解

ITリテラシーには、主にコンピュータやネットワークの仕組みを理解し、それらを日常業務や生活に活かす力が求められます。具体的にはパソコン操作やスマートフォン活用、ソフトウェアの使い方などを含む基本的な技術知識を指します。
基礎的な知識がある程度身についていることで、ソフトウェアのアップデートやトラブル対応がスムーズに行え、作業効率を高めることが可能です。さらに、セキュリティ意識を高めるきっかけにもなるため、総合的なリテラシーの土台となります。
現代社会におけるITリテラシーの役割
ITリテラシーは、現代社会におけるビジネスにとって重要な役割を担っています。現代社会では情報がオンライン上に集約され、業務効率化や新たなサービス開発が急速に進んでいます。こうした環境下でITリテラシーが不足していると、情報の検索や整理がうまくいかず、意思決定の正確性やスピードが低下する可能性があります。
一方で、ITに精通している人材や組織は、クラウドやAIなどの新技術に柔軟に対応し、市場競争力を高めることができます。ITリテラシーが担う役割は、単なる知識の習得に留まらず、ビジネスや社会をリードするうえで欠かせない基盤となっています。
生成AIの基礎知識についてもっと詳しく
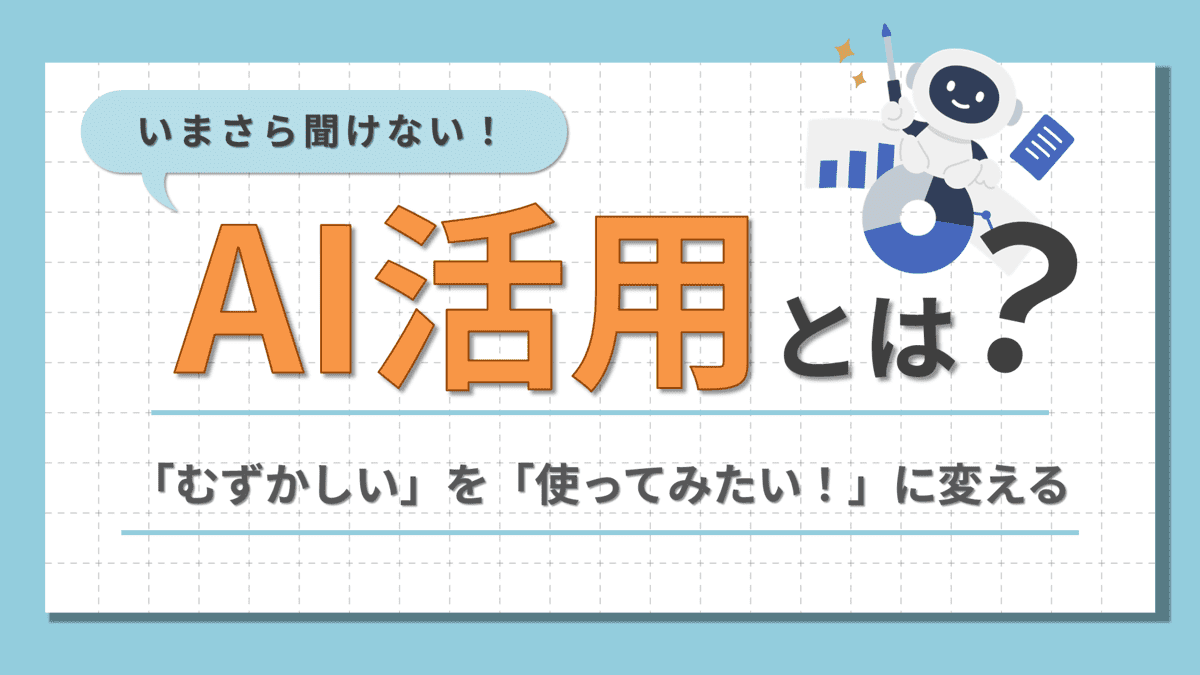
いまさら聞けない!AI活用とは?
企業の業務効率化や意思決定のサポートにおいて、AIの導入がますます重要になっています。AIの基本的な知識から、従来型AIと生成AIの違い、AIアシスタントの活用方法まで幅広くご紹介しています。
ITリテラシーの要素
ITリテラシーを細分化することで、具体的に身につけるべき能力を把握します。
ITリテラシーは複数の要素に分解でき、それぞれが相互に影響し合うことで総合的な能力を形成します。独立して見れば小さな領域でも、実務や日常シーンで必要となる場面は幅広いです。
要素ごとに学習計画を立てることで、漏れなく知識を獲得できる点が利点といえます。すべてを一度に完璧に身につけるのは難しいため、まずは自分や組織に不足しているポイントを明確にすることが効果的です。
ここでは4つの要素を紐解いていきましょう。
- コンピュータリテラシー
- 情報リテラシー
- インターネットリテラシー
- メディアリテラシー
コンピュータリテラシー
パソコンやスマートフォンを日常的に扱ううえで、OSの操作方法やソフトウェアの導入・運用などの基本スキルは欠かせません。これらの知識がある程度あると、トラブル発生時に原因を推測し、対処方法をスムーズに見つけやすくなります。
また、日頃からOSの更新やソフトウェアを活用できる環境に慣れておくことで、企業全体のIT推進にも寄与します。特に業務のデジタル化が進む中で、社員全員が必要最低限のコンピュータリテラシーを持っていることは大きな強みとなるでしょう。
コンピュータリテラシーと言う言葉は、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)で以下のように定義されています。
コンピュータを操作して目的を達成する能力を指す。インターネットを用いて情報を探索、精査する能力を含む。
引用:ITLS(IT Literacy Standard)案の策定について IPA
情報リテラシー
膨大な情報がインターネット上に存在する現代では、必要な情報を効率よく探し出し、正しく分析して活用する力が欠かせません。企業では情報をいち早く収集し、マーケットや顧客の動向を的確に把握することで、競合に先んじた対応が可能になります。
さらに、情報の信頼性を見極める力も含まれます。誤った情報を鵜呑みにしてしまうと、業務上の判断ミスや不正確なコミュニケーションにつながるため、日頃から情報リテラシーを磨いておくことが重要です。
IPAでは以下のように定義されています。
情報を探索、精査、活用する能力する能力。
引用:ITLS(IT Literacy Standard)案の策定について IPA
インターネットリテラシー
インターネットリテラシーはSNSやオンラインコミュニティの活用手段を理解し、適切に利用するための能力です。投稿内容ややり取りの公開範囲を意識しながら、情報セキュリティを担保したうえで発信する意識が求められます。
企業においても、社内・社外のコミュニケーション手段としてSNSが活発に利用されるケースが増えています。いざというときに迅速かつ正確な発信ができるよう、組織や個人がデジタルリテラシーを高めることが不可欠です。
IPAでは以下のように定義されています。
インターネットを用いて情報を探索、精査、活用する能力する能力。
引用:ITLS(IT Literacy Standard)案の策定について IPA
メディアリテラシー
テレビやウェブ、ソーシャルメディアなどから得られる情報を正しく理解し、発信の影響や意図を客観的に評価する能力も重要です。断片的な情報だけでは正しい判断を下せないため、様々なメディアを横断的にチェックして比較検討する習慣が求められます。
メディアリテラシーを習得することで、デマに惑わされずに自社や顧客に関する情報を見極められるようになります。その結果、適切なマーケティング施策や企業方針の策定にもつながるでしょう。
IPAでは以下のように定義されています。
メディア情報を(クリティカル=批判的に)評価・識別する能力。
引用:ITLS(IT Literacy Standard)案の策定について IPA
また、自身が正確な情報をメディアに発信する能力もメディアリテラシーに含まれます。例えば、企業組織のアカウントで上方発信する際には、誤解を与えないように内容を精査する必要があります。このように、情報を受け取る力はもちろん、発信する能力もメディアリテラシーとして重要なスキルなのです。
ITリテラシーの重要性
ビジネスや日常生活で必要不可欠なITリテラシーに関して、その重要性を探ります。
ITリテラシーが高いと、業務効率化や問題解決のスピードが向上します。さらに、オンライン上のリスクを軽減できるため、セキュリティ事故などの被害を未然に防ぐ効果も期待できます。
また、急速に進化するIT環境に対応する力があれば、新しいツールやサービスを活用してビジネスを変革するDXの推進にも弾みがつきます。個人レベルでも、キャリア形成に大きな影響を及ぼす重要スキルとなるでしょう。
職場でのITスキル需要

企業では、顧客データの分析やプロジェクト管理など幅広い場面でITの活用が進んでいます。たとえば、クラウドマネジメントツールやデータ分析ソフトを使える社員が多いほど、意思決定の精度が高まりやすいです。
また、リモートワークの増加により、オンライン会議ツールやチャットツールを適切に活用できる人材への需要がさらに高まっています。こうした職場環境の変化に適応するためにも、ITスキルが欠かせない時代となりました。
情報管理能力と問題解決能力の重要性
日常業務だけでなく、緊急時の対応でもITリテラシーの高さが実を結びます。情報漏えいを防ぐセキュリティ対策や、システムの障害発生時に的確なトラブルシューティングが行えるかどうかが重要なポイントです。
このような管理能力と問題解決能力が組織内に浸透していれば、セキュリティ面での大きな事故を回避し、事業継続性を高めることができます。結果として、信頼性の高い企業イメージの確立にもつながるでしょう。
ITリテラシーを高めることで生まれる4つのメリット
ITリテラシーの向上によって得られる、具体的かつ大きなメリットを紹介します。
ITリテラシーを身につけると、社内外におけるやり取りの円滑化や、作業の自動化などの恩恵を受けやすくなります。これは業務効率の向上やコミュニケーションロスの削減につながり、組織全体の生産性を底上げする効果も期待できます。
さらに、ITに対する理解が深いほど、新しいテクノロジーを試す際のハードルも下がり、積極的なデジタル施策に取り組めます。以下では、特に注目される4つのメリットを具体的に見ていきましょう。
1.セキュリティ意識の向上とリスク回避
ウイルス感染やデータ漏えいを防ぐためには、社員一人ひとりがセキュリティ意識を持つことが不可欠です。ITリテラシーを高めると、パスワードの管理や怪しいメールの判別など、基本的な対策レベルが全社的に上がります。
こうしたリスク回避の意識が身につけば、情報資産の保護と企業ブランドの維持につながり、不測の損害を防止できるでしょう。
2.生産性の向上と業務の効率化
会計処理や在庫管理など、従来はアナログ作業に時間がかかっていた業務をデジタル化すると、ミスの削減と効率化に直結します。ITリテラシーがある程度備わっていれば、新しいシステムの導入もスムーズに進むでしょう。
最適なツール選定から運用まで、担当者がしっかりとITを使いこなせることで、組織全体のパフォーマンス向上につながる点が大きなメリットです。
3.最新技術への適応力強化
AIやクラウドシステムなど、新しいテクノロジーは常に進化を続けています。ITリテラシーが高いほど、これらの技術を積極的に取り込んで、業務改革やサービス拡充に活かせる柔軟性が生まれます。
最新のIT動向をキャッチアップできる組織や個人は、市場競争力を維持・強化し、顧客のニーズに即応できる強みを育むことができます。
4.DX(デジタルトランスフォーメーション)の促進
DXは単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルや企業文化まで含めた大規模な変革を意味します。ITリテラシーが高いメンバーが揃えば、デジタル技術による抜本的な改善案が生まれやすくなります。
結果として、社内の意識改革や部門横断的なコラボレーションがスムーズに進み、革新的なプロジェクトの実現につながるのです。
ペーパーレスについてのおすすめ資料

ITリテラシーが低いことによるリスク

ITリテラシー不足は、様々なトラブルや企業損失につながるリスクがあります。
ITリテラシーが低いままでは、セキュリティリスクや業務上のロスが増えてしまいます。スタッフが情報を正しく取り扱う方法を理解していなければ、重大なインシデントが起きる可能性も高まり、社会的信用を失う事態に発展しかねません。
また、デジタル化の波に乗れないことで、競合他社と比べて市場での存在感が弱まるリスクも否めません。ここでは、リテラシー不足が招く具体的なリスクを見ていきましょう。
1.セキュリティ事故やデータ漏えいのリスク
パスワードの使い回しや不適切なファイル共有など、基本的な対策を怠るだけでも大きな被害につながります。情報漏えいが発生すると、顧客や取引先の信頼を損なうだけでなく、高額な賠償金が生じる可能性もあります。
こうした事故は、一度起きると取り返しがつかないケースが多く、企業にとっては致命的なダメージとなるでしょう。
2.業務効率の低下と競争力の低下
IT活用が十分でない組織では、コストのかかるアナログ作業が長引き、担当者の負荷も大きくなります。これにより、同業他社に比べてスピード感のある取り組みができず、ビジネスチャンスを逃すことが増えるでしょう。
結果として、企業全体の競争力が下がり、さらなる売上の減少や人材流出につながるおそれもあります。
3.情報の誤用や判断ミスの増加
ITリテラシーの低い人が情報を適切に扱えない場合、誤ったデータを基に重要な決定を下してしまうリスクがあります。特にマーケティングや財務などデータ駆動型の業務では、大きな判断ミスにつながる可能性も少なくありません。
デマや虚偽情報に振り回されることも含め、ITリテラシー不足は取り返しのつかない損失を生む危険性が高いといえます。
4.社内外コミュニケーションの障害
オンライン会議システムやチャットツールの使い方がわからず、対面式のやり取りしかできないと、リモートワーク下での意思疎通に支障が出ます。連携ミスや情報共有の遅れが重なると、大きなプロジェクトほど進捗が滞るリスクが高まります。
また、社外のパートナーや顧客とのやり取りに遅れが生じることで、信頼性にも影響しかねない点は見逃せません。
業務改善についてもっと詳しく

desknet's NEO ユーザー事例集
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOを活用し業務改善に成功したお客様の導入事例を集めました。
ITリテラシーを高めるための有効な方法
自社や自身のITリテラシー向上へ取り組む際に役立つ、おすすめの方法をまとめます。
ITリテラシーの向上は、日常的な学習と経験の積み重ねが不可欠です。組織的に研修を行うだけでなく、社員が主体的にスキルアップできる仕組みを整えておくことが効果的です。
資格取得やオンライン学習サービスの活用を通じ、知識の体系化とモチベーションの維持を図るのも一つの方法です。以下では、代表的な方法を確認していきましょう。
1. ITリテラシーセミナーや研修の実施
企業や各種団体が提供するITリテラシーセミナーや研修を受けることで、体系的に基礎から学べます。初心者向けの講座が多いため、ITが苦手な社員でも安心して参加できる点が魅力です。
また、社内に専任のIT担当者や研修担当を置くことで、実践的な内容をカスタマイズしながら教育機会を得られます。
2. IT関連試験への挑戦
ITパスポートや基本情報技術者試験は、ITの基礎レベルを証明できる資格として広く認知されています。試験対策を行う過程で、ネットワークやセキュリティ、データベースなど、幅広い知識を学ぶことができます。
合格を目指すことで学習のモチベーションが高まり、組織内でも資格を持つ人材が増えれば、社内のITリテラシー水準が底上げされるでしょう。
3. ITツールや最新技術に触れる環境づくり
普段から実際にITツールや最新技術に触れることで、理解度は飛躍的に向上します。具体的にはチャットツールやグループウェアなどを導入し、従業員が日常的に利用できるように促すことが効果的です。
現場で使うITシステムや情報共有手段を整備し、誰でも気軽に学習・トレーニングできる空気を作ることで、組織全体のリテラシーが自然と高まっていくでしょう。
まとめ
ITリテラシーを高めることは、企業の競争力や個人のキャリアアップに直結します。
現代のビジネス環境においては、デジタル技術の活用が当たり前になりつつあります。そのため、ITリテラシーの向上は生産性やセキュリティ面でのメリットをもたらすだけでなく、最新技術への適応やDX推進の加速という形でも恩恵をもたらします。
一方で、リテラシーが不足していると、大きなセキュリティ事故や機会損失を招きやすくなることも事実です。セミナーや資格取得、最新ツールの導入など複数の方法を組み合わせ、自分自身や組織のITリテラシーを高めていきましょう。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
グループウェアについてもっと詳しく

desknet's NEO 製品カタログ
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOの製品ご案内資料です。
更新日:
「業務効率化」について
もっと読む
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221


 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部