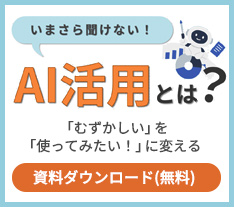業務引継ぎをスムーズに行うための効果的な方法

プロジェクトリーダーの新任や、部署異動による重要な業務を前任者から引き継ぐ際は、スムーズな業務引継ぎを実現しなければなりません。しかし、「引継ぎがうまくいくだろうか」「業務引継ぎで大事なことは何だろう」といった不安を感じる人も多いのではないでしょうか。できれば、伝達ミスや準備不足が原因で業務が停滞する事態は避けたいものです。
本記事では、業務引継ぎの意味や目的を再確認しながら、その方法や引継ぎ時の注意点、起こり得るトラブルと対策などについて解説します。
業務引継ぎとは
業務引継ぎとは、前任者の業務知識や関連技術を後任者に継承することを指します。例えば、チームリーダーの交代や、退職・休職・部署異動による担当者の変更時に、次の担当者への業務引継ぎが発生します。
業務引継ぎの重要性
業務引継ぎが重要な理由を3点紹介します。
- 業務の中断を防止する(業務の継続性)
- 業務効率や・生産性を落とさない(業務負担の軽減)
- ミスやトラブルの防止(顧客や取引先からの信頼維持)
業務引継ぎは、業務の中断を防ぐこと、業務品質の維持に欠かせません。
例えば、業務担当者が途中で変わっても、引継ぎが適切に行われていれば、顧客対応をスムーズに継続させることができます。プロジェクトメンバーが入れ替わっても、プロジェクトの進行が止まることはありません。引継ぎにより、新しい担当者が即時対応できるため、業務全体の流れを止めることがないのです。引継ぎは、単に情報伝達をするだけではなく、安定した業務進行を保つために必要な準備です。
引継ぎ不足による影響とリスク
業務引継ぎに不足があると、後任者が業務内容を理解できず、業務に大きな影響を与える恐れがあります。例えば、顧客が前任者へ質問した内容を引継ぎ忘れた場合です。顧客は後任者へもう一度同じ質問を繰り返さなければなりません。これが企業に対する不信感に繋がります。また、プロジェクトにおけるタスクの引継ぎが不足していると、仕事の漏れが発生し、プロジェクト全体の進行が遅れるでしょう。引継ぎ不足という原因が明確になるまでの間、チーム内での混乱が生じる場合があります。
引継ぎ不足は組織全体の業務効率を悪化させ、生産性が低下するリスク要因となり得ます。内容によっては企業経営の安定性に深刻な影響を及ぼすこともあります。
引継ぎがもたらすメリット
適切な業務引継ぎが行われていれば、後任者はスムーズに業務を継続できます。質の高い引継ぎが、ミスやトラブルの発生率を低減させるためです。情報共有が徹底されていれば、後任者とチームメンバーの信頼関係も高まり、コミュニケーションを円滑にするメリットも享受できます。
また、引継ぎが細部まで行われていれば、業務上の「分からないこと」を減らせます。メンバーが後任者に「教える」手間も軽減する上、後任者は自信を持って業務に当たることができるでしょう。例えば、顧客は「担当が変わったこと」を意識せずに、満足なサービスが受けられます。これは、顧客満足度(CS)向上にも繋がるものです。
顧客満足度(CS)については、「顧客満足度(CS)とは?CS向上のための効果的な戦略と取り組みを解説」にて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
業務改善についてもっと詳しく

desknet's NEO ユーザー事例集
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOを活用し業務改善に成功したお客様の導入事例を集めました。
効果的な業務引継ぎのコツ、成功のポイント
業務のスムーズな引継ぎを行うためにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、引継ぎを行うステップとコミュニケーションの方法を中心に説明します。
業務引継ぎのステップと準備
ここでは、引継ぎの基礎として、そのステップや準備を確認していきます。
1.業務引継ぎ計画の策定

効率的な業務引継ぎを行うための最初のステップは、計画の策定です。引継ぎ事項をすべて洗い出しながら、引継ぎ開始日と完了日を設定していきます。必要な資料やデータを集め、後任者へ伝える項目の優先順位を明確にしておくことが重要です。同時に、業務内容を精査して、非効率な作業を単純化したり、無駄な手順を整理したりしておくとよいでしょう。
また、複雑な作業や業務理解が難しい内容に関しては、相手の立場を考えながら、「なぜその作業が必要なのか」「〇〇と関連している手順だから省けない」など、理由もわかりやすく具体的に整理しておくことがコツです。これにより、後任者が理解しやすくなります。
引継ぎ内容に応じて、引継ぎのスケジュールを調整しましょう。引継ぎは、想定より時間がかかることもあります。スケジュールミスにより「短時間による中途半端な引継ぎ」も起こりがちです。業務内容を確実に伝えられるように、できるだけ余裕を持った日数を確保することが大切です。
2.業務内容の整理と文書化
引継ぎ開始日までに業務内容を整理し、資料やマニュアルとして業務引継書を作成します。口頭だけの曖昧な引継ぎにならないように、各種丁寧に文書化しておくことが大切です。業務を進める上でチェックすべき過去データなどは資料としてまとめ、作業の流れはマニュアル化します。業務の中で発生し得る特殊な問題や手順は、対応策まで記載しておくこともポイントの一つです。
業務引継書に記載すべき基本的な内容には、以下のような項目が挙げられます。
- 前任者(引継ぎ者)の名前
- 後任者(引継ぎを受ける者)の名前
- 業務の目的と全体像
- 作業手順
- 作業の期間と期限
- 業務に関わる関係者(チーム、部署、取引先、顧客など)の名前と連絡先
- 業務に関するデータの保存先
- 過去のトラブル履歴と対処法
- 引継ぎ者独自のノウハウ
記載する内容は完結に読みやすく書くことが大切です。例えば、「〇〇の作業のときに、どこを見たらよいのか」が理解しやすい資料であれば、後任者の不安を軽減できます。
3.担当者の決定
担当者の決定は、引継ぎの準備として重要です。引継ぎを行う者と引継ぎを受ける者をはっきりさせておくことはもちろんですが、引継ぎが行われたことを確認する者も必要です。複雑な業務内容や、部署間を横断する業務などがある場合は、立会をする第三者も決めておくとよいでしょう。例えば、システム部門の業務内容に営業部門が関連する業務などでは、システム部門の新任と、業務に関わる営業部門の担当者を引き合わせる必要があります。組織内で混乱を招かないために、「業務引継ぎが行われること」を把握している担当者(上司など)も決めておく必要があるのです。
各担当者を明確にし、責任者を据えることで、「必要な情報が伝わらない」リスクを最小限に抑えられます。
コミュニケーションの重要性
業務引継ぎにおいて、コミュニケーションはスムーズな引継ぎを成功させるために不可欠です。ここでは、引継ぎ時の直接的なコミュニケーションや、質問を受け付ける体制づくりについて見ていきましょう。
直接的なコミュニケーションと確認
業務の引継ぎ内容を正確に伝えるために重要なのは、直接的なコミュニケーションと確認です。前任者は一方的に教えるのではなく、後任者の理解を確認しながら進めなければなりません。後任者は、不明点を残さないように、分からない部分や解釈に迷いがある点を質問することが大切です。また、後任者のスキルや経験によっては「自分が分からない部分が、分からない」という場合もあるでしょう。そのため、事例を用いながら後任者に問題解決をさせ、理解度をチェックするなどの施策も必要です。例えば、「何か質問はありますか?」という問よりも、「〇〇の場合はどのように対処しますか?」といった質問が有効な場合もあります。
質問を受け付ける体制づくり
一通りの引継ぎが終了しても、後任者が業務を一度ですべて理解することは難しいでしょう。また、新しい業務に慣れるまでには、どうしても時間がかかります。そのため、一定のサポート期間を設けるなどのフォロー体制をつくることが重要です。チャットやメールなどで質問を受け付ける環境を準備したり、複雑な業務ならば現場へ一緒に出向き、疑問点を解消したりすることも必要でしょう。
このような体制づくりは、新しい業務に取り組むハードルを下げ、後任者へ心理的な安心感を与えます。また、引継ぎ直後のトラブル発生を低減することもできるでしょう。もちろん、サポート期間も引継ぎスケジュールに組み込んでおくことが大切です。
ペーパーレスについてのおすすめ資料

業務引継ぎ時によくあるトラブルと注意点
業務引継ぎでは、準備や情報の不足が起こりがちです。また、引継ぎのための情報共有手段が情報漏洩などのトラブルを招くこともあります。ここでは、引継ぎをスムーズに進めるために、引継ぎ時の注意点とトラブル対策について見ていきましょう。
よくあるトラブル事例
よくあるトラブル事例としては以下が挙げられます。
- 引継ぎが期限までに間に合わない
- 必要な資料が準備できていない
- 連絡事項が不足している
- 業務が属人化している
- 業務データの情報漏えいリスクが発生している
業務引継ぎの際の注意点
上記のような、よくあるトラブルを避けるための注意点を説明します。
1.引き継ぎの期間を十分にとる
人事異動や退職による引継ぎでは、慌ただしく資料作成やミーティングに十分な時間が設けられないことはよくあります。引継ぎ期間があまりにも短いことは、引継ぎが上手くいかないリスクが高まります。例えば、「時間がないから端折って説明する」「伝えるべき内容の網羅性に欠ける」などの原因になってしまうのです。
組織として、引継ぎの重要性を理解し、業務が滞らないよう、余裕を持ったスケジュールで計画しましょう。
2.引継ぎ資料の作成を行う
業務引継ぎにおけるトラブルの原因には、業務マニュアルや引継ぎ参考資料の内容の不足もよく挙げられます。資料やデータが揃っていない状況では、後任者が業務を開始した際に混乱したり、業務を止めてしまったりする原因に繋がります。
このようなトラブルを引き起こさないためにも、チェックリストを作成しておくとよいでしょう。チェックリストには、引継ぎをする業務に必要な書類やデータ、優先順位付きのタスク表などを記載します。このチェック表を基に、引継ぎにかかる工数や作業負担を逆算して十分な引継ぎスケジュール期間を立てるのです。また、進捗状況が確認できる作りにしておくことで、引継ぎの進捗管理にも活用できます。
3.コミュニケーションを取り、伝達の抜け漏れをなくす
異動や退職などの慌ただしい中でも、前任者と後任者の間でコミュニケーションを取ることも大切です。マニュアルや引継ぎ資料だけに頼ると、前任者からの一方的な説明となってしまいがちです。後任者による業務の理解を深めたり、質疑に答えるためにも、リモートや対面での引継ぎの機会を設けたいものです。
4.個人ではなくチームで業務情報を共有する
とある人にしかわからない業務、その人にしかできない業務、これらは属人化された業務と呼ばれます。属人化された業務は、担当者が異動、退職するような事態以前に、多忙であったり事情があって休んでしまった場合にも、その業務が停止してしまいます。それは組織としてのリスクとなり得ます。
属人化を防ぐためには、日ごろから複数人の担当やチームで業務情報や手順の共有を行うことも対策の一つです。
5.情報漏えいの防止策の徹底
業務引継ぎを行う際に利用するデータや資料、マニュアルの共有方法は、引継ぎ時における注意点の一つです。例えば、前任者が退職する場合、引継ぎ完了後にアクセス権限を付与したままにしておくと、部外者がデータにアクセスできる状況になってしまいます。
このようなリスクを抑えるためには、引継ぎに使うデータの取り扱いに関するルールを明確化して、関係者で遵守することが大切です。アクセス権限の適切な設定を行うことや、引継ぎ完了後に不要な権限を速やかに削除することを検討しましょう。また、資料やマニュアルを含めたデータは、暗号化やパスワード設定を施して管理し、不正アクセスによる情報漏洩を防ぐ対策も行いましょう。
引継ぎを円滑にするためのツール
スムーズな業務引継ぎには、ツールの活用が欠かせません。ここでは、引継ぎ時に使えるプロジェクト管理ソフトやクラウドストレージ、コミュニケーションプラットフォームについて見ていきましょう。
プロジェクト管理ソフトとクラウドストレージ
業務引継ぎには、進捗管理や資料、マニュアルのファイル管理などが必要です。プロジェクト管理ソフトやクラウドストレージを活用することで、引継ぎ作業が効率的になります。
例えば、「業務引継ぎ」を一つのプロジェクトと捉えることで、プロジェクト管理ツールを活用できます。TrelloやAsanaなどのITツールを使えば、引継ぎのタスク管理や進捗管理を可視化できるため、引継ぎ内容の抜け漏れ防止用チェックリストとして利用可能です。期限の設定やタスク担当者の割当機能を使って、複数の後任者に対する引継ぎ作業を効率化する活用方法もあります。工夫次第で、後任者がプロジェクト全体の流れや関係者を把握しやすくなるでしょう。
また、さまざまな資料の活用にはクラウドストレージの活用が欠かせません。Google DriveやDropboxなどを使えば、業務引継ぎに必要なファイルを一箇所にアップロードして一元管理できます。クラウドストレージにすべての引継ぎ資料が集約されていれば、情報の分散も防ぐことができるため、効率的な管理が可能です。アクセス権限の設定も可能なため、セキュリティに配慮したアクセス管理ができます。
コミュニケーションプラットフォームの活用
引継ぎに関するスムーズなコミュニケーションには、ビジネスチャットツール(Slack、Chatwork、ChatLuck等)をはじめとしたコミュニケーションプラットフォームの活用をおすすめします。ビジネスチャットツールを利用すると、リアルタイムに連絡が取れる状態を作れます。チャネルやグループチャットの作成機能は、業務引継ぎに関するやり取りの一元的な集約に便利です。
また、グループウェアを活用すれば、業務引継ぎの内容やスケジュールを社内で簡単に共有できます。例えば、desknet's NEOでは、ポータルやワークフロー、スケジュールなどに加え、自社の業務に合わせたアプリをノーコードで作成できるAppSuiteが提供されています。既存のツールが業務引継ぎに使いにくい場合は、自社の業務に合わせたアプリを作成してもよいでしょう。
業務引継ぎにおけるコミュニケーションも、ツールを活用することで効率化することが可能です。
紹介したツールについては、「仕事の効率化を図るための最適ツールガイド」でも触れていますので、あわせてご覧ください。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
まとめ
業務引継ぎは、業務の連続性と品質を維持するために不可欠です。後任者がスムーズに業務を遂行できるように、前任者は十分な準備と計画を行う必要があります。業務引継ぎが不十分であると、後任者のミスや不安要素になります。さらに、業務の遅延や停止が発生したり、ステークホルダーに不信感を抱かせたりする可能性もあるのです。
業務引継ぎをスムーズに行うためには、前任者と後任者の両者が引継ぎの重要性や方法を理解することが大切です。引継ぎ時に起こりやすいトラブルやその対策も事前に把握しておきましょう。また、引継ぎにおける資料やマニュアルの一元管理、コミュニケーションには、ツールの導入もおすすめです。
グループウェアについてもっと詳しく

desknet's NEO 製品カタログ
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOの製品ご案内資料です。
更新日:
「業務効率化」について
もっと読む
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221


 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部