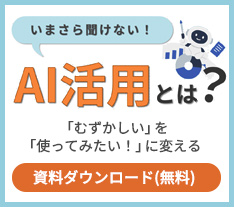研修報告書の書き方ガイド|
伝わりやすい例文も紹介
研修報告書を書くとき、「どのような内容を盛り込めば良いのだろう」「上司に評価される書き方はあるのだろうか」といった悩みを持つ方は少なくありません。報告書作成の理由や目的を曖昧にしたまま書き始めると、記載すべきポイントが抜けたり、全体的にまとまりがなく理解しにくい文章になったりすることもあります。
本記事では、研修報告書の目的や重要性、基本的な構成を交えながら、ポイントや書き方の例文などを紹介します。
研修報告書とは

研修報告書とは、受けた研修内容や成果を記録する文書です。研修レポートとも呼ばれます。ここでは、社会人が作成する機会が多い研修報告書の目的や重要性について見ていきましょう。
研修報告書の目的と重要性
研修報告書の主な目的は、研修で身に付けた知識やスキルを整理するとともに、チームや社内でそれらを共有することです。また、報告書は上司やチームリーダー、同僚に向けた報告手段としても使われます。研修報告書をまとめながら、内容の反復学習を行う方法としても効率的です。
そもそも研修は、人材育成のために行われます。そのため、研修報告書は、その研修がどれほど効果的であったか測ることや、研修内容・成果を明確にするために重要な報告書なのです。
また、研修報告書は、課長などの管理職や人事担当者などが、「研修で何を学んだのか」「どのように実務に生かせるのか」を判断する材料にもなるため、今後の参考資料としても重要です。例えば、今回の研修が本人やチームにとって有用であれば、次回の研修計画に盛り込むことも検討されるでしょう。逆に実用的でないならば、別の方法でのスキルアップ計画を立てなければなりません。
研修報告書にはどのような目的や役割があるのかを意識して書くことで、価値のある報告書を作成できます。
アプリを使った日報運用についてのおすすめ資料

AppSuiteならできる!日報の悩みはアプリで解消
紙を使った日報作成や提出、取りまとめや集計にまつわる負担など、日々の日報や報告書に関するお悩みは、AppSuiteのアプリで解消できます。本資料では、アプリを使った日報運用で業務効率を改善した事例もご紹介しています。
研修報告書の基本構成
研修報告書の書き方は会社によってさまざまで、テンプレートの種類によっても異なります。共通して重要なことは、「どのようなことを報告すべきか」を把握しておくことです。ここでは、研修報告書に書くべき基本構成について見ていきましょう。
表紙と目次
報告書の「タイトル」や「作成日」、「氏名」や「所属部署」などを記載します。目次には、見出しとページ番号を記載しておくことで、全体の構成が一目で分かるようにしておきましょう。
序文
研修を受講した背景や目的を簡単に説明します。研修に対する期待や意気込みを記載しても良いでしょう。
研修の概要
「受講した研修のテーマ」や「主催者」、「実施形式」などを記載します。研修がどのような環境で行われたかを把握する情報です。
研修の目的
研修で得たい知識や、習得が期待されるスキルや成果について記載します。読者が、研修の概要と合わせて読むことで、研修の全体像を把握できます。
開催期間と場所
研修の日程と実施場所、またオンライン研修の場合はオンラインプラットフォームなどについて記載します。
参加者情報
研修に参加した「人数」や、参加者の「所属部署」「役職」「経験年数」などを記載します。研修の対象者がどのような層であったかを把握する項目です。
研修内容の詳細
研修全体のスケジュールや、流れを具体的に記載します。どのような研修が行われたのかを明確に伝える項目です。
講義内容
各講義のテーマや講師名、主なトピックについて記載します。この項目で、研修の内容や重要なポイントを整理します。
実習やワークショップ
研修で実施された演習内容や、グループワークでの成果物を記載します。取り組みの具体的な説明を記載する項目です。
質疑応答とディスカッション
研修内での質疑応答や議論の内容を記載します。ここで記載する内容は、今後同様のテーマを扱うときに参考資料として役立ちます。
学びと成果
研修で得た知識やスキルを具体的に記載します。業務へどのように活用できるかも合わせて書くと良いでしょう。
今後の課題と改善点
研修を受けて明らかになった課題や、取り組むべき改善点を分析して記載します。業務における次のアクションプラン策定に役立ちます。
研修の感想
研修全体の感想や印象、理解度などを記載します。研修に期待していた内容への期待や満足度のギャップに触れるのも良いでしょう。
ポジティブな経験
研修を受けて良かった点や成功体験などを記載します。ポジティブな経験を記録に残すことで、研修の意義や印象を伝えることができます。
改善が必要な点
研修を振り返り、自身の取り組み方に対する反省点がある場合は、具体的に記載します。次の研修を受ける際の注意点を記録できます。
結論と今後の展望
研修の総括を記載します。受けた研修に意義があったか、学んだことを今後どのように生かすのかをまとめます。
参考資料や付録
研修で使用した資料や配布物などを記載します。
上記項目すべてを記載することが必須ではありませんが、研修報告書の精度を上げるための項目として参考にしてください。
ペーパーレスについてのおすすめ資料

効果的な書き方のポイント
研修報告書は、読む人(上司やチームメンバーなど)が読みやすく、理解しやすい構成と簡素な文章を心がけることが大切です。ここでは、書き方のポイントについて見ていきましょう。
明確な目的設定

研修報告書を書く際には、明確な目的を記載することが重要です。目的をはっきりさせることで、「誰に、何を、なぜ伝えるのか」が明確になるため、報告書全体に一貫性が生まれ、読みやすい構成を作りやすくなるのです。伝えるべき情報が整理され、読み手にとって理解しやすい報告書が作成できます。
例えば、「上司」に「研修内容とそこで得た知識とスキル」が、「チーム全体で業務に生かせるものであることを伝える」という目的を設定してみましょう。研修報告書の冒頭にこれらが明記されているだけで、報告書の内容の方向性が最初に分かるため、読み手も「読み取るべき内容」を意識しやすくなり、伝わりやすくなります。
要点を押さえたまとめ
研修の内容をすべて書くのではなく、重要な事項に絞って記載することも読みやすい研修報告書を書くポイントの一つです。長い一文や、冗長な説明を避けて簡素にまとめることで、読み手が内容を理解しやすくなります。また、一つの見出しに記載するテーマは一つに絞って、情報を整理しましょう。
具体的な事例の活用
講義やディスカッションの際に印象に残った具体的なエピソードや成功体験、行動などを書くと、印象に残りやすい報告書になります。また、実際の業務でどのように使えるのかを挙げることで、研修で得た知識の活用がイメージしやすくなるでしょう。例えば、研修で学んだプロジェクト管理方法を、現在進行中のプロジェクトに当てはめて記載すれば、報告書の説得力が上がります。
読み手を意識した表現
研修報告書は、読み手を意識して作成しなければなりません。上司やチームメンバーが理解しやすい表現選びが重要です。対面でのコミュニケーションと同じように、曖昧な表現や専門用語の多用を避けるなどの配慮をしましょう。できる限り簡素な言葉を使うことで、内容が伝わりやすくなります。また、箇条書きや短い段落を意識して書くことで、読み手が必要な情報を見つけやすくなり、読みやすい報告書になります。
簡潔で明確な表現
簡素で明確な表現をすることで、情報が伝わりやすくなります。一つの文章に一つの情報だけを書く「一文一義」を意識するだけで、スッキリした文章を書くことができます。また、修飾語をできるだけ減らし、曖昧な表現や無意味な情報は取り除きましょう。内容が明確に分かる文章を心がけることで、読者が必要な情報を短時間で読み取れるようになります。
図や表の活用
文章だけでは表現しにくい複雑な内容には、図や表を活用しましょう。視覚的に整理することで、読み手は内容を理解しやすくなります。図や表には簡単なキャプション(説明文)を付けておくと親切です。図表を交えた構成は、報告書全体の質を向上させます。
プロフェッショナルな外観
研修報告書の外観は、内容と同じくらい重要な要素です。一貫したデザインやフォーマットを使うことで、報告書としての信頼性も高まります。例えば、フォントや見出しのスタイルを統一することや、行間などを整えるなどの配慮が挙げられるでしょう。また、上下左右の余白を適切に設定することで、視認性が高まります。読みやすいレイアウトを意識した外見は、読み手に好印象を与えるポイントです。
生成AIの基礎知識についてもっと詳しく
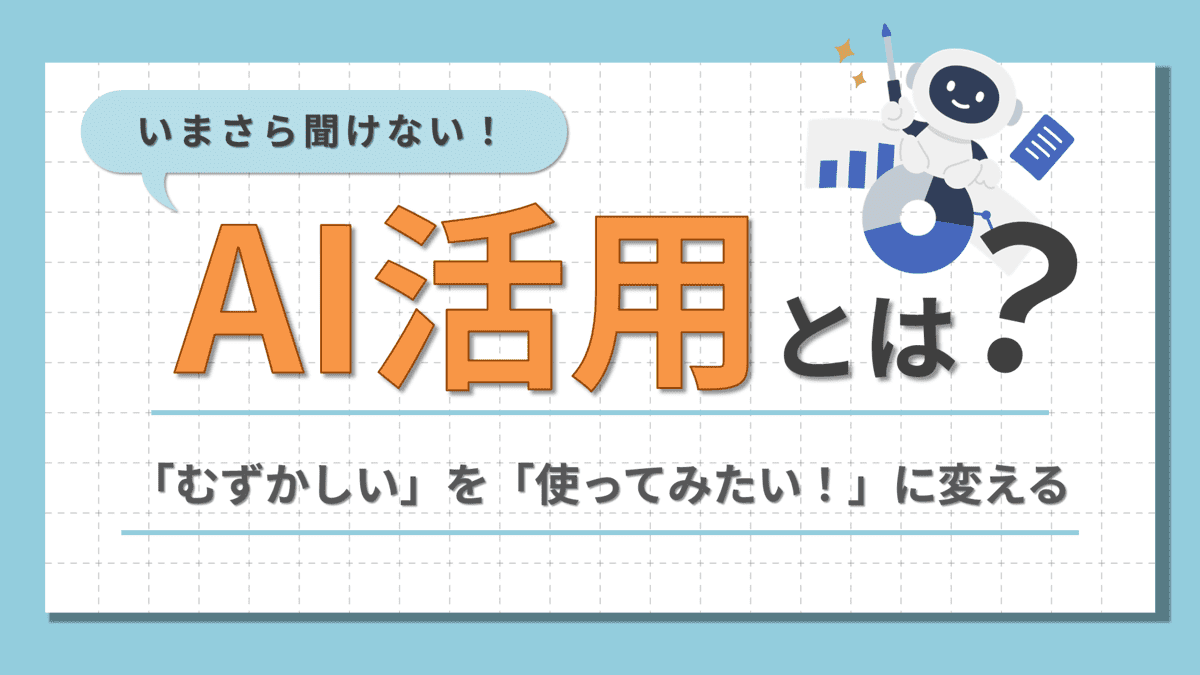
いまさら聞けない!AI活用とは?
企業の業務効率化や意思決定のサポートにおいて、AIの導入がますます重要になっています。AIの基本的な知識から、従来型AIと生成AIの違い、AIアシスタントの活用方法まで幅広くご紹介しています。
研修報告書の書き方例
研修報告書の書き方の例を見ていきましょう。ここでは、研修受講者の例文と、研修実施者の例文に分けています。両者の記載項目は異なりますが、それぞれの立場に合わせて参考にしてください。
研修報告書の例文(受講者)
研修受講者の報告書の例文です。
| 表紙と目次 | YYYY年MM月DD日 プロジェクト管理研修受講報告書 〇〇部 田中太郎 <目次> 1. 〇〇 ………2 2. 〇〇 ………3 3. 〇〇 ………4 ~~~ |
|---|---|
| 序文 | 受講した「プロジェクト管理研修」についてご報告いたします。 |
| 研修の概要 | ● テーマ:プロジェクト管理スキルの向上 ● 対象:〇〇部 ● 主催者:人事部 ● 講師:山田一郎 氏 ● 実施形式:オンライン形式 |
| 研修の目的 | プロジェクト管理を効率化するための具体的なスキル習得が目的です。 |
| 開催期間と場所 | ● 開催期間:2024年12月1日~12月2日 ● 開催場所:Zoomを用いたオンライン形式 |
| 参加者情報 | ● 所属部署:〇〇部 ● 参加人数:10名 ● 内訳:一般社員8名、主任2名 |
| 研修内容の詳細 | 研修は以下の3部構成で行われました。 1. プロジェクト管理の理論(講義) 2. ケーススタディを用いた実践演習 3. 成果発表とディスカッション 各セッションでは、具体的な事例を基にプロジェクト管理の解説が行われ、〇〇や□□の理解を深めることができました。 |
| 講義内容 | 講義では、プロジェクト管理ツールの活用法や〇〇について学びました。 特に、〇〇の作成方法や、□□の効率化についての解説にて、△△を深く学ぶことができました。 |
| 実習やワークショップ | ワークショップでは、〇〇を題材としたケーススタディに取り組みました。 私たちのチームは、〇〇の課題を解決するために、△△を提案しました。 |
| 質疑応答とディスカッション | 実際のプロジェクトでの問題点を質問し、具体的な解決策として〇〇の手法と△△ツールの活用方法を教えていただきました。 ディスカッションでは、他の参加者の経験から〇〇のケースにおいて□□で問題解決をした経緯など、△△について多くの学びを得ることができました。 |
| 学びと成果 | この研修を通じて、プロジェクト管理における〇〇スキルを習得しました。 これは、□□業務に適用できるものです。特に、△△は、今後の〇〇業務で活用できると感じています。 |
| 今後の課題と改善点 | 研修を通じて、〇〇業務における□□や△△の課題が明確になりました。 今後は、〇〇を導入し、□□のスムーズな実践を目指したいと考えています。 |
| 研修の感想 | 研修全体を通じて、〇〇についての実用的な知識とスキルを得ることができました。 講師の丁寧な説明や、出された具体例が特に印象に残っています。今後もこうした研修に積極的に参加したいと思える研修でした。 |
| ポジティブな経験 | グループディスカッションで他の参加者と意見交換を行う中で、〇〇からの視点やアイデアを得ることができました。 特に、□□さんの△△に対する解決策は非常に参考になりましたので、自分の業務の〇〇に取り入れたいと思います。 |
| 改善が必要な点 | オンライン形式での講義を受ける中で、一部音声が聞き取りにくい場面がありました。 オンライン形式の研修を受ける際には、通信環境をしっかりと確認する時間を設け、事前準備を万全に整える必要があると感じました。 |
| 結論と今後の展望 | 今回の研修で得られた〇〇の知識を生かし、△△業務の効率化を図ります。 また、チーム全体での□□管理の仕組みを強化したいと考えています。今後も継続的に研修や独学で新たなスキルを習得し続けることで、自身の成長と組織全体の目標達成に貢献していきます。 |
| 参考資料や付録 | 今回の研修で使用した資料は以下の通りです。 ・「プロジェクト管理入門」(配布資料) ・ワークショップ用課題シート(PDF形式) ・研修スライド(講師提供資料) |
研修報告書の例文(実施者)
研修実施者の報告書の例文です。
| 表紙と目次 | YYYY年MM月DD日 プロジェクト管理研修実施報告書 人事部(教育推進担当者) 佐藤 景子 <目次> 1. 〇〇 ………2 2. 〇〇 ………3 3. 〇〇 ………4 ~~~ |
|---|---|
| 序文 | 実施した「プロジェクト管理研修」についてご報告いたします。 |
| 研修の概要 | ● テーマ:プロジェクト管理スキルの向上 ● 対象:〇〇部 ● 主催者:人事部 ● 講師:山田一郎 氏(〇〇コンサルタント) ● 実施形式:オンライン形式 |
| 研修の目的 | 本研修は、〇〇部10名を対象に、プロジェクト管理スキル向上を目的として実施しました。 |
| 開催期間と場所 | ● 開催期間:2024年12月1日~12月2日(計10時間) ● 開催場所:オンライン形式(使用ツール:Zoom) |
| 参加者情報 | ● 所属部署:〇〇部 ● 参加人数:10名 ● 内訳:一般社員8名、主任2名 |
| 実施内容 | 研修は以下の3部構成で進行しました。 1. プロジェクト管理の理論(講義) 2. ケーススタディを用いた実践演習 3. 成果発表とディスカッション |
| 受講者の学びと成果 | 研修後のアンケート結果にて、以下のような成果が確認できました。 ● 受講者の90%が「研修内容を〇〇の業務に活用できる」と回答 ● △△の活用方法に対する理解の深まり ● 受講者間の意見交換を通じて、△△における新しい視点での問題解決策が得られた |
| 改善が必要な点 | 通信環境の問題で、一部の受講者が音声の途切れを確認しています。また、グループディスカッションの時間が足りず、意見を十分にまとめることができなかったとの意見もありました。 改善点として、以下が挙げられます。 ● 受講者へ、通信環境の事前準備に関する通達を徹底 ● 主催側にて、研修実施スケジュール調整の強化 |
| 参考資料や付録 |
・「プロジェクト管理入門」(配布資料) ・ワークショップ用課題シート(PDF形式) ・研修スライド(講師提供資料) |
研修報告書を書く際の注意点
研修報告書を作成する際には、いくつかの注意点を抑えておく必要があります。
まず、報告書を作成する目的を見失わないことです。研修報告書は単に「作業」として作成するのではなく、自身の学びを振り返りながら、上司や同僚へ「研修の成果と応用の可能性を伝える」ことを念頭に置かなければなりません。誰に何を伝えたいのかを明確にし、価値のある報告書の作成を目指しましょう。
また、報告書の信頼性を高めることも意識しましょう。そのためには、曖昧な記憶や憶測で書くことを避け、情報を正確に記載する必要があります。誤字脱字がないことや文章の読みやすさも、報告書の信頼性向上に繋がります。
研修報告書が、業務にどのような影響を与えるのか、今後のプロジェクトの効率化や改善にどのように役立てられるのかを考えながら構成し、外観も含めて内容を精査することが大切です。
執筆の流れとスケジュール管理
研修報告書を価値あるものに仕上げるためには、作成の流れを把握したスケジュール管理が大切です。ここでは、研修報告書作成における3つの具体的な手順を見ていきましょう。
1. 事前準備
最初のステップは事前準備です。研修報告書を書くために必要な資料などの情報を集めましょう。講師から配布された資料や、研修中にメモした内容を整理しながら、一カ所に集約すると良いでしょう。執筆中に必要な資料をすぐに取り出せるようにしておくことで、書きながら資料を探すという無駄な手間が省けます。
また、本記事で解説している基本的な構成や書き方を把握しておくことで、報告書の全体的な流れを掴むことができるでしょう。記載すべきことを抽出して全体の骨子を作成し、各見出しに記述する内容を明確にしておくことで、執筆がスムーズになります。さらに、各見出しの内容に対応した資料を紐付けておけば、「この見出し内容を書くときには、この資料を見る」ことがすぐに判断できますので、執筆作業を効率的に進められます。
2. 執筆期間の設定
事前準備が完了して、全体像が見えてきたら、執筆期間を設定しましょう。ここでのスケジュール設定と管理が、研修報告書の完成度と信頼性を左右します。ギリギリのスケジュールを設定してしまうと、突発的な業務が発生した場合や、想定よりも時間がかかったときの焦りが、報告書の精度を下げてしまう可能性があるためです。もちろん、研修報告書の提出には納期があるでしょう。その中でスケジュールを立てて管理していくためには、執筆ボリュームから逆算して計画する必要があります。
例えば、全体のスケジュールが5日間の場合は、最後の見直しに1日を取り、残りの4日間で執筆します。以下の項目は内容が確定しているため、時間はかからないでしょう。
- 表紙と目次
- 序文
- 研修の概要
- 研修の目的
- 開催期間と場所
- 参加者情報
- 参考資料や付録
自身で文章を考える以下の項目に、執筆時間を割り当てるようにしましょう。
- 研修内容の詳細
- 講義内容
- 実習やワークショップ
- 質疑応答とディスカッション
- 学びと成果
- 今後の課題と改善点
- 研修の感想
- ポジティブな経験
- 改善が必要な点
- 結論と今後の展望
1日目は、「表紙と目次」から「参考資料や付録」を仕上げ、2日目は「研修内容の詳細」から「質疑応答とディスカッション」までを、3日目に「学びと成果」から「研修の感想」、4日目に「ポジティブな経験」から「結論と今後の展望」を書くなど、見出しごとに執筆日を分割すると、時間的にも精神的にも負担が軽減します。
3. 全体の見直し
執筆が完了したら、報告書全体を見直しましょう。例えば、報告書全体の流れが順序立てて構成されていることや、流れがスムーズであることを確認します。また、各見出しに記載した内容が十分であるか、参考資料を見ながら抜け漏れがないことを確認することも大切です。
文法のミスや誤字脱字のチェックと修正も、このステップで行います。可能であれば、チームメンバーや上司など第三者に読んでもらい、フィードバックを受けることで、自分では気づかなかったミスや漏れを把握するという方法もあるでしょう。研修報告書の完成度を高めるためにも、全体の見直しをしっかりと行いましょう。
よくある問題点とその解決策
研修報告書を作成するときには、構成やスケジュール管理などで、さまざまな問題に直面することがあります。ここでは、よくある問題点とその解決策について、以下2点を見ていきましょう。
- 文章のまとまりが悪い
- 期限内に書けない場合
文章のまとまりが悪い
研修報告書を書いていく中で、「文章のまとまりが悪い」と感じることがあります。それは、読み手にとっても分かりにくい文章です。この問題を解決するためには、全体の見出しの内容を整理して、情報を混在させないようにすることが重要です。
例えば、「今後の課題と改善点」と「研修の感想」の見出しで、両方の内容に改善点と感想を書いてしまうと、内容の重複が生じます。その結果、読みにくい文章になってしまうのです。それぞれの見出しの内容は、「何にフォーカスして書くか」を意識して、書き分けることが大切です。先述したように一文一義を守ることも、文章のまとまりを改善するポイントです。
また、読み直しと修正を繰り返すことで、文章の整合性を高めましょう。書き終わった文章は、時間を空けてもう一度読むと、修正点が見えてきます。Wordなどに搭載されている音声読み上げ機能で、執筆した文章を「聞く」方法もおすすめです。
期限内に書けない場合
スケジュールの遅延は、研修報告書作成時に起こりがちです。期限内に書き終えられない可能性がある場合は、報告書の提出先へ早めに相談をしましょう。その際、現在の進捗状況や、提出可能な期日も併せて伝えることが大切です。
どうしても書けない項目がある場合は、チームメンバーや上司にサポートが必要なことを相談しましょう。自分だけで解決しようとして、時間ばかりが過ぎていくことは避けなければなりません。「がんばり」よりも「報告書を完成させる」ことの方が大切だからです。
また、研修報告書を書く際には、最初からチームや上司に進捗状況を共有しながら進めると安心です。スケジュールと進捗を周りが把握していれば、サポートも受けやすくなるでしょう。
まとめ
研修報告書は、研修内容や成果の記録、自身の学びの振り返り、それらをチームメンバーや社内に共有するために重要な報告書です。目的を明確にして適切な構成を作成し、執筆することで、上司や同僚などの読み手が理解しやすい報告書を書くことができます。まずは、研修報告書の目的や基本構成、書き方のポイントを押さえて、スムーズに執筆できるように準備することが大切です。書いた研修報告書は、再度読み直し、誤字脱字や内容の漏れなどを確認して、信頼性の高い報告書を作成しましょう。
組織の業務改善に役立つグループウェア desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
グループウェアは、社内の情報共有に最適なツールです。グループウェア desknet's NEOは、スケジュールやワークフロー、社内ポータルをはじめとした27機能が標準で備わっており、社内の情報共有に関する課題解決、業務効率の改善に役立ちます。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
DXを推進する desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
グループウェアについてもっと詳しく

desknet's NEO 製品カタログ
情報共有、業務の改善・デジタル化、セキュリティ管理などの社内の課題を解決できるグループウェア desknet's NEOの製品ご案内資料です。
更新日:
「業務効率化」について
もっと読む
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221


 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部