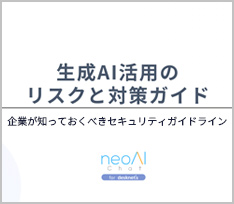EOSL対応とは?保守期限切れに対する選択肢と対応策
サーバーやネットワーク機器、ソフトウェアの運用に関わる「EOSL」や「EOL」という言葉。これらは、メーカーによる販売や保守サポートが終了することを指します。また、同時に障害が発生した時に運用上立ち行かなくなるリスク、併せてセキュリティリスクが格段に高まります。
しかしながら、EOSLのタイミングは新たな製品導入やシステムの移行計画を進める契機にもなり得ます。サポート終了とライフサイクルの変化を単なるコスト増と捉えず、技術刷新や業務改善の好機として捉える発想も大切です。
本記事では、EOSL対応に必要な基礎知識から具体的な対処法までを整理し、保守期限切れを迎える製品のリスク軽減と持続的なシステム運用を実現するためのヒントを提供します。
EOSLの基礎知識
EOSL(End of Service Life)とは

EOSLは、IT機器やソフトウェア製品のメーカーが提供するサポートや修理対応が打ち切られ、部品の調達や問い合わせ対応などが行われなくなる状態を指します。これに伴い、障害が発生した場合の復旧時間が長引きやすくなり、事業継続への影響が大きくなる点が問題となります。
運用の安定性の観点から、この時期までに必要な計画を立てないと、予期せぬ故障やセキュリティ脆弱性への対応が困難になる可能性があります。EOSLは、製品のライフサイクルの一部であるため、企業としては早めにそのスケジュールを把握し、システムの更新や延長保守、代替策の検討などを進めることが重要です。
どうなる?どうする?ソフトウェアのサポート終了 サポート切れのリスクと対処方法とは
EOSLに似た言葉に、EOL、EOS、EOEといったものがあります。ここからはEOSLとこれらとの違いについて説明します。
EOL(End of Life)との違い
EOLは製品の寿命そのものが終了することを示し、販売や開発がストップする段階を指します。
EOSLと比較すると、EOLのほうがより包括的な概念であり、製品全体のライフサイクルの終焉を意味します。一方でEOSLは保守や修理といったサービスの終了を指し、メーカーによってはEOL後も一定期間サポートを提供するケースもあるなど、両者のスケジュールや意味合いを混同しないように整理しておく必要があります。
EOS(End of Sale)との違い
EOSは製品の販売が終了する状態を示します。
サポート自体はまだ継続可能なこともあります。つまり、販売を打ち切っても、既存ユーザー向けに保守契約が残っている場合があるため、即座にEOSLになるわけではありません。メーカーの発表するスケジュールをよく確認し、いつどの段階でサポートが終了するのかを把握することが重要です。
EOE(End of Engineering)との違い
EOEは、製品の新規開発やエンジニアリングサポートが打ち切られる状態を指します。
ソフトウェアの不具合修正や機能追加が行われなくなるタイミングを意味します。セキュリティアップデートの提供も停止される場合が多いため、サイバーリスクが高まる要因にもなりやすいでしょう。EOSLとは異なる基準で設定される場合もあり、メーカーのアナウンスを確認しながらシステムのアップデート計画を立てることが必要です。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
ファイル転送機能で大容量ファイルも簡単・安全・確実に送信
グループウェアの乗り換えについてのおすすめ資料
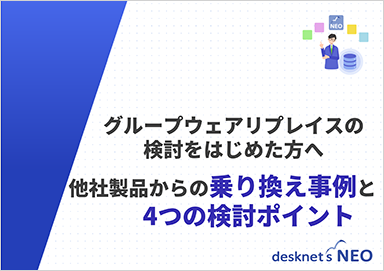
他社製品からの乗り換え事例と4つの検討ポイント
グループウェアリプレイスを検討されているお客様向けに、他社製品からdesknet's NEOへ乗り換えた事例とグループウェア乗換時の4つの検討ポイントをまとめました。
EOSL・EOLで想定されるリスクと影響
メーカー保守が終了した後のリスクを把握し、運用面やセキュリティ面での影響を見極めることが重要です。
保守終了後の製品に障害が起きた場合、部品調達や修理担当者を確保するのが困難となり、復旧までに時間がかかる可能性があります。その間、システムが停止すれば業務に大きな支障をきたし、損失が発生することもあるでしょう。加えて、メーカーからのアップデートが停止されることでセキュリティパッチが提供されず、攻撃者が脆弱性を悪用するリスクが高まります。このような事態を未然に防ぐためにも、事前の備えが欠かせません。
メーカーサポート終了による運用上のリスク発生
EOSLを迎えるとメーカー側に修理用の部品がない、または供給体制の維持が困難になるため、不具合時に迅速対応ができなくなる場合があります。さらに、障害復旧のための知見が社内に不足している場合は、対応の遅延が長期化しやすく、ビジネス全体に影響が及ぶ可能性があります。
アップデート停止によるセキュリティリスク発生
メーカーサポートがなくなると、新たに判明したセキュリティ脆弱性に対してパッチが供給されず、システムが脆弱な状態のまま稼働することになります。これにより、不正アクセスやマルウェア感染のリスクが高まり、最悪の場合は重要なデータや業務システムが大きな被害を受けることも考えられます。定期的にセキュリティ対策を行うか、別のサポート形態を検討し、リスクを最小限に抑える必要があります。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
ファイル転送機能で大容量ファイルも簡単・安全・確実に送信
EOSL対応の主な選択肢

EOSLが近づいた際、どのような対応策を選ぶかは企業ごとの運用方針やコスト、リスク許容度などに大きく左右されます。
保守期限が切れた後のシステム運用を考えるにあたり、最も安全性と拡張性が高いのは新しい機器や環境への移行ですが、その分投資コストもかかります。一方、第三者による延長保守や現状のまま使用を継続するなど、さまざまな選択肢が存在するため、自社の状況に合わせて慎重に判断することが求められます。
以下に主な対応策と、それぞれのチェックポイントについてまとめます。
リプレイス(新規機器・システム導入)
EOSLのタイミングでハードウェアやソフトウェアを新しいものへ置き換える方法です。最新技術を取り入れることでパフォーマンスが向上し、次世代のサポートやアップデートが受けられるのが大きなメリットです。ただし、初期投資の大きさや運用移行時の混乱を最小化するために事前準備が欠かせません。
リプレイスを行う場合のチェックポイント
まずは予算の確保や経営陣の了解を得ることが重要です。さらに、新規システムと既存システムの互換性を検証し、移行時に業務が滞らないようスケジュールをしっかり組み立てましょう。移行に伴うデータ移行計画、トレーニング体制の整備なども忘れてはいけません。
アップグレードやクラウドへの乗り換え
製品のバージョンアップやクラウド移行を行うことで、最新の機能や継続的なサポートを得られる可能性があります。オンプレミス環境に比べて、クラウドでは拡張性と費用対効果が期待できるため、リプレイスよりもスピーディに導入できる場合もあります。ただし、自社アプリケーションとの互換性や既存資産の運用方法を十分に検討する必要があります。
アップグレードやクラウドへの乗り換えを行う場合のチェックポイント
クラウド導入時には、サービスレベル契約(SLA)を確認し、可用性やセキュリティ基準を満たすかどうかを判断してください。オンプレミスからの移行に際しては、データ移行方法や運用ルールの見直しも不可欠です。コストメリットのみならず、将来的なメンテナンス性を踏まえた総合的な検討が求められます。
第三者保守(延長保守)サービスの導入
メーカーサポート終了後も、保守専門ベンダーから継続的に修理や点検、問い合わせ対応を受けられるのが第三者保守サービスです。メーカーに比べて保守料金が抑えられるケースがあり、コスト最適化や長期的なサポート継続が期待できます。しかしながら、対応製品の種類や技術力、部品調達力などはベンダーにより差があるため、導入前にしっかりと比較検討を行う必要があります。
第三者保守サービスを選ぶ場合のチェックポイント
最も重視すべきは、過去の対応実績と部品供給体制です。サービスレベル合意(SLA)やサポート範囲について明確に取り決められているか、契約前に確認しましょう。サポート終了までの期間が長期化するほど、ベンダーの信頼性が運用の安定性を大きく左右します。
保守切れのまま継続使用
新たな設備投資を極力回避したい場合、保守期限が切れた状態のまま使用を続ける選択肢もあります。ただし、障害が起きた際の長期停止リスクやセキュリティの懸念など、デメリットが大きいため、慎重な判断が必要です。本格的な移行計画の準備期間を確保するための一時的措置としてならば検討する余地はありますが、中長期的にはリプレイスや第三者保守の導入を含めた再検討が望ましいでしょう。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
ファイル転送機能で大容量ファイルも簡単・安全・確実に送信
EOSLに備えて進めておくべきこと
EOSLは必ず訪れるステージだからこそ、事前に準備を進めてリスク低減につなげることが重要です。

EOSLへの備えとして重要なのは、サポート終了となる製品の把握と、具体的な対策に必要な時間を確保することです。システム規模が大きいほど対策に時間がかかる傾向にあるため、早めに情報収集とプランニングを始めましょう。適切なタイミングで関係者を巻き込み、段階的に移行計画を策定することで、混乱を最小限に抑えられます。
サポート終了日や契約状況の洗い出し
まずは自社で保有しているハードウェアやソフトウェアの保守契約内容と終了時期を一覧化し、どの製品がいつEOSLを迎えるかを明確にしましょう。重要度の高いシステムほど手厚いサポートが必要ですが、保守形態や契約内容が曖昧だとスムーズに計画を立てられません。情報を一元管理し、必要に応じて見直す体制を整えることが大切です。
必要な予算・リスク評価の実施
リプレイスやアップグレードには一定のコストが発生し、第三者保守を利用する場合にも保守契約の費用がかかります。また、保守を切ったまま使い続ける場合のリスクコストを数値化して、ダウンタイムなどによる損失を見込むことも重要です。これらの費用対効果を定量的に把握し、経営層と相談しながら適切な選択肢を探ることが求められます。
ステークホルダーとの調整と余裕を持った計画
システムの移行や保守契約の大幅な変更は、例えば業務フローや利用部門にまで影響が及ぶため、関連部署や利害関係者との調整が不可欠です。特に、経営層やIT部門以外の部署にも必要な情報を共有し、合意形成を図りましょう。時間的な猶予を十分に取りながら計画することで、トラブルを回避しつつ、円滑なEOSL対応を実現できます。
まとめ:EOSL対応を長期的なIT戦略に組み込む
EOSLは避けて通れない問題である一方で、新たな技術導入やIT方針を見直す好機としても捉えることができます。
EOSLを前向きに捉え、未来志向のIT戦略と合わせて検討することで、企業システムの信頼性向上だけでなく、さらなる業務効率化やビジネス拡大の可能性を探ることができます。リプレイスやアップグレードだけでなく、第三者保守の利用や継続使用など、さまざまな手段があることを知り、自社に合った選択肢を組み合わせることが大切です。サポート期限を正しく認識し、計画的に次のステップを踏み出すことが、安定した運用とコストメリットの両立につながるでしょう。
スケジュール管理からノーコード開発まで 業務課題をワンストップで解決、
ファイル転送機能で大容量ファイルも簡単・安全・確実に送信
グループウェアの比較についてのおすすめ資料

最新グループウェア徹底比較
国内外を含む、5つの主要なグループウェア製品について、機能面、価格面から徹底比較した資料です。グループウェアの最新動向、各製品の比較検討にぜひお役立てください。
更新日:
すべての機能は今すぐ無料で
体験できます
電話でお問い合わせ
平日9時 - 12時 / 13時 - 18時
- 横浜本社 045-640-5906
- 大阪営業所 06-4560-5900
- 名古屋営業所 052-856-3310
- 福岡営業所 092-235-1221


 執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部
執筆者:株式会社ネオジャパン 編集部